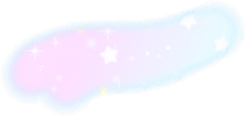
08 違類の違う絶望
魔法が遣えるようになってから、は急速に跡部たちと仲良くなった。魔法遣いであるにも関わらず無能のレッテルを貼られてきた。そのが、魔法で人の命を救ったのだ。は自信を持つことが出来、晴れやかな気持ちになれた。また、魔法を跡部たちに賞賛された事で、彼らとの距離も縮まった。人と距離を置いていただったが、跡部たち以外の生徒とも話すようになり、笑みを浮かべる事も多くなった。(今までずっと魔法の練習をしてばかりで、友達付き合いとか最近はずっと……。周りに目を向けるって新鮮。でも、楽しい。認めてもらえて……嬉しいな)
の魔法はその後から消えずく、空を飛び続けている。とは言っても人前では飛ぶことは無い。同じ日本でありながら、今がいるのは同じ日本とは違う。魔法そのものが無い。そんな世界で魔法を遣って空を飛べば、メディアが放っておかないだろう。大混乱は避けたい。最も、免許を持っていない18歳以上の魔法遣いが魔法を遣う事は、の世界でも犯罪に値する。積極的に人前で魔法を遣う気にはなれなかった。
(魔法はこれからも私にとって大切だけど、跡部くんたちにも言われたし、隠しておかなくちゃ……)
周りに迷惑を掛ける事は避けたい。
1人で昼休みに多目的室に入る。今日は珍しく修学旅行実行委員会は開かれない。担当の教師が出張に出ているためだ。黒板には修学旅行の注意事項が昨日のまま書き残されていた。
は黒板に近い前の席に座ると、鞄から委員会に提出する報告書を出した。まだ半分書き途中で、旅行先であるイギリスの生活習慣などの項目がまだ埋められていなかった。昨日のうちに書いておけば良かったのだが、昨日は頭痛がしてしまい、風邪かもしれないからと教師に委員会の途中で早退させられてしまったのだ。自分はそこまで頭が痛いとは感じていなかったのだが、確かに調子は悪かったので早退に応じた。
最低限の筆記用具が入っているペンケースからシャープペンを取り出す。丁寧に空いてしまっている欄に文字で埋めていった。
教室にはのペンの音だけが響いた。ペンの音など普段は人の話し声やドアの開閉の音、廊下を走る生徒の足音などの雑音で消されてしまっている。だが、今は耳横で感じるような大きな音に感じられた。それが不思議。だがすぐに答えは見つかった。ピタリと手が止まる。
(そっか……。いつもは皆がいるから……)
今日あった出来事を大声でいちいち報告してくる岳人。
大声で騒ぐのを注意する忍足。
寝ているけれど寝言を呟くジロー。
寝ているジローを叩き起こそうとする跡部。
そんなやり取りを見て笑っている滝。
部活での後輩指導について質問をする日吉。
何か困ったことが無いか聞いてくる長太郎。
宿題が終わらなくて頭を抱えている宍戸。
(皆、何で私と一緒にいるんだろ?)
魔法が遣えるから?魔法遣いが珍しいから?
(魔法は遣えても、ほんのちょっとだけ。この世界で魔法は珍しいかもしれないけれど、何度も私が飛んでいるところは見たはず……)
日本にいたときも、イギリスにいたときも、の周りに人はいた。だが、大半が自分ではなく祖母に対して関わりのある人間だった。第三者で本人と関係を持ちたいと思っていた人物は、全く思い浮かばなかった。
(先生は私が研修を受けなかったらきっと無関係だったろうな)
そう思うと、今の状況がおかしな事に思えてくる。自分に近づく人間の本心がわからない。
「怖い……」
また魔法が遣えなくなったら、彼らはどうするのだろうか?
「何がですか?」
「?!」
ぽつんと呟いただけで、まさか反応が返ってくるとは思ってもいなかった。驚きのあまり椅子から落ちそうになってしまう。顔を上げると多目的室の入り口に2人の後輩が立っていた。
「日吉くん、鳳くん」
名前を呼ばれた日吉は『どうも』とそっけなく挨拶をし、長太郎は丁寧に会釈をした。
「廊下を歩いていたら、丁度先輩の姿が見えたものですから」
長太郎はにっこりと人懐っこい笑顔を浮かべた。日吉は無表情のままで、この2人が並ぶとかなり対照的なのがわかる。それでも一緒にこうしているのは、どこか似ているところがあるからかもしれない。
は手元を見る。すっかり書類は文字で埋められていた。ペンケースにペンを仕舞うと立ち上がった。
「様子見に来てくれたんだ。ありがとう」
「さっき、『怖い』って言ってませんでした?」
「あ……」
やはり聞かれていたようだ。言葉にするつもりなど無かったのに、自然と零れていた。は少し困った顔をして口を開こうとしては閉ざす。長太郎はそれを見て日吉を肘で小突く。
「止めろよ日吉。先輩が困っているじゃないか」
「いいよ。気にしないで」
気にしないで欲しい。まさか彼らの気持ちを疑うなんて事、知られたくない。
「もしかして、先輩の魔法の事ですか?」
「えっ?あ、ああ、そう。魔法の事」
上手く話が逸れたので、はこのまますり替える。
「……私、落ちこぼれだから」
「どういう意味ですか?」
「前にも言ったけど、私、魔法で空しか飛べないじゃない?そのうえ箒が無いとダメなんだもの。魔法士の免許を取ったって、魔法士の事務所なんか開けない。開いたって誰も依頼になんか来ないって、そう言われた……」
の中にある魔法に関する記憶は、良いものが少ない。思い出すだけで、胸が締め付けられる。希望を持って懸命に取り組んできただけに、のショックは計り知れなかった。
日吉はそんなことかというように溜め息をついた。
「そんなの、もっと努力するしか無いじゃないですか」
日吉の野望はテニスで跡部から頂点を奪い取ること。つまり【下克上】だ。そのためには努力は惜しまないし、ずっとそうやって上だけを見つめてきた。
は既に日吉の言葉を予想したのか、苦笑するだけだった。
「そうよね。キミは―――キミたちなら、そう言うわよね」
笑っていたが、影のある寂しい表情だった。だが、直ぐにの表情はいつもの明るい笑顔に戻った。
「さぁさぁ、そろそろ教室に戻ろう!もう授業になるし、ね」
日吉と長太郎の腕をぐいぐい引くと、半ば強引に多目的室を後にした。丁度が教室に戻った頃、学園内に授業開始の鐘が鳴り響いた。
それから次の日、は忍足とジローと下駄箱前で出会い、一緒に下校することになった。この日は教師たちの大きな会議があるので、午前中で生徒たちは全員下校となった。
の首にはコスモス色のマフラー、ジローの首には真っ赤なロングマフラーが巻かれていた。もう冬だ。頬に当たる風も冷たい。忍足はここに来る前に少し後輩たちにテニスを教え、トレーニングとしてマラソンもしていたためまだ頬が赤くなっていた。制服の上着も腕に抱えてある。
街もすっかり冬の装いといったところで、すれ違う人々もコートを羽織っていたり、白い息を吐いていた。
「忍足くん、寒くない?」
「平気やで。もうめっさ暑いくらいや」
「途中から跡部と競争してたもんねぇ〜。意外と忍足って負けず嫌いなところあるC〜」
「負けるんは誰だって嫌やろ」
大人っぽい容姿におっとりとした関西弁を喋る忍足からは想像もつかないことで、は意外に感じた。そして思わず笑ってしまった。
「あはは……。忍足くんってそういうところもあるんだ」
「どういう意味やねん。オレかて熱くなることもあるわ。オレもただの中学生なんやし」
「ごめんね」
謝罪をしながらもはおかしそうに笑ってしまう。
「そういえばちゃん、最近飛んで無くない?また見たいC〜」
「でもこのへんでいきなり飛んだりしたら、みんなが驚いちゃうよ」
ジローは魔法にかなり興味津々な方だ。こうして良くに魔法を見たいと言う。
「…………」
魔法の話をした途端、忍足が急に黙ってしまった。それから少々考える素振りを見せる。その目はやや真剣そうに見えて、は声を掛ける。
「あの、どうかした?」
「ちゃん」
「?」
いつも以上に低い声だった。
「ちゃんの世界にも、魔法を遣えない人もいるんやろ?」
「え?ああ、いるわよ。魔法を遣えない人の方が魔法遣いよりも多い感じね。魔法遣いの中でも、遣える魔法もは違ってくるわ」
魔法は御伽話のように呪文を唱えるわけでも、すごい道具を使うわけでも無い。魔法遣いとしの素質、魔法の血が流れているかどうかで決まる。魔法が発現するのもその人間が幼い頃だったり、大人になってからだったりとまちまちだ。そして、遣える魔法も。人が1人1人違うように、魔法遣いもまた1人1人違う。
忍足はの答え聞いて妙に納得したような顔をした。
「魔法って、例えば魔法の遣えない人が一生懸命育てて咲かせた花も、あっという間に出せるんか?」
「まぁ、そういう魔法が遣える人もいるから出せると思う。私みたいに能力に偏りがある人もいるけれど、万能型っていう何でも本当に魔法で出来る人もいるよ」
「そうなんや……」
「忍足くん?」
益々彼が何を言いたいのかわからなくなった。ジローも同じ気持ちらしく、首を傾げてしまっている。
「魔法ってずるいわ」
忍足の口から発せられた言葉は、の予想していないものだった。
「だってそうやろ?他の人が必死こいてやったことも、パーっと一瞬でやってしまうやなんて」
「そ、そんなつもりじゃ……!」
ジローは忍足の発言に声を上げようと口を開いたが、ぐっと堪えて唇を閉じた。
はまさかこのような事を言われるとは思っていなかったので、何とも言えずに困惑してしまっている。だが、忍足はそんな様子のを見てもお構いなしに続けた。
「ちゃんは自分で思ったこと無いん?」
「それは……そんな、事……」
「なぁ、魔法を遣うのってずるいって思ったこと無いんか?」
「忍足」
忍足の腕はいつの間にかジローの手に捕まっていた。握られた腕はギシっと音を立ててしまいそうなほどに強く握られていた。ジローの表情は怒っているものでは無かった。だが、その目に強い想いを感じて忍足は睫毛を伏せた。そして困惑してしまったままのの肩を軽く叩いた。
「悪かったなぁちゃん。気にせんといてな。ただホンマにちょっと気になっただけなんや」
「え……?う、うん」
「ジロー、オレ先に帰るわ。ほな2人とも、またな」
ジローの手から解放されて忍足は、の言葉も待たずに街の人込みの中へと消えていった。残されたは、ただその真っ黒な髪の後ろ姿を見つめることだけしか出来なかった。
完全に忍足の姿が見えなくなった後、ジローは優しい口調で言った。
「ごめんね、ちゃん」
「そんな、ジローくんは全然悪く無いし……忍足くんだって、そうだよ」
ずるいなんてことが言われるとは思っていなかったとはいえ、言われた経験が無いわけでは無い。空が飛べる。でも、箒が無いと飛べない自分にでさえ、魔法を遣えない一般人にとってはそのように捉えられてしまうことはあった。思い出すともやもやとした気分になって、悲しくなった。
忍足の言うことは、魔法を持たない人ならば誰でも覚える感情なのかもしれない。魔法が無いこの世界では益々そう感じてしまうのかもしれない。だから、この疑問が出ても当然だった。
ジローは忍足が去った先を見つめながら言った。
「忍足はね、テニス部で活躍してたとき、【天才】って呼ばれてたんだ」
「天才?」
「そう。ちゃんみたいに転入してきたんだけれど、当時の正レギュラーだった先輩をアッサリ倒して変わりに正レギュラーになったんだ」
「すごい!」
「違うよ。ちっともすごくなんか無い」
「ジローくん……?」
ジローの目は昔を思い出すような雰囲気で、それでいてどこか辛そうに見えた。
「『アッサリ』っていうのは嘘。忍足は強くなるために努力してた。その成果がただ実を結んだだけ。でも、試合結果は6−0だったから、きっとそう見えて、倒された先輩自身も『相手は天才だったんだ。だから自分が負けてもおかしくない』って言った」
の見ていた忍足には、そんな事を感じさせなかった。しかし、確かに彼は特に弱みというものが無いようにも見えていた。
「忍足は何をしても天才っていうたった2文字が何をしてもついてまわってる。いくら努力して、良い結果が出たとしても、天才だから出来て当たり前、ってね」
は自分を振り返る。何をしてもダメな自分。ようやく特技らしい特技が見つかったが、それは出来そこないの魔法。同じ魔法遣いにも軽視され、一般人からも疎まれる。そんな位置に自分は立っていた。
そして忍足は、努力が実を結んでいた。それにも関わらず、懸命に努力してきたということが認められない。天才の文字が、努力してきた全てを無にしていく。それはとは異なるようで似た絶望。
「忍足はね、ちゃんのこと好きだよ」
「うん」
「それに、『ずるい』って言うのはさ、きっとその人のことを認めているからだと思う」
「うん」
「忍足の事、嫌いにならないでね」
「うん……!」
が今まで受け取った『ずるい』という言葉の中で、1番胸に染み入る言葉だった。
とジローが忍足と別れ、人の行き来の激しい駅に差し掛かったとき、人々がざわついていることに気がついた。それも皆不安そうな表情をしていて、中にはスマホの画面を必死に見つめている人もいる。それに人々の視線はある方向に向けられていた。
「どうしたのかな?」
「ん?あ、ちゃん!アレ!!」
「何?……あッ?!」
空を見上げると、ビルの隙間から雷雲のような真っ黒の煙がモクモクと大量に流れ出ていた。風によってここまで運ばれてきたのだろう。だが、ここからそう遠くは無いと感じた。煙に乗ってパラパラと白い塵のようなものが降ってきた。それは紙のようでもあり、燃え尽きた木材のようにも思えた。
「これって、まさか……!」
がまさに言おうとしていた言葉を、近くに立っていたサラリーマンが携帯に向かって言った。
「近くのデパートで火事があったらしいな。お前は大丈夫か?……そうか、ちゃんと避難できているんだな、良かった」
もジローも次の瞬間には走り出していた。消防車の特徴あるサイレンの音が鳴り響いている。次々に赤い車は現場に向かっていった。
火事が起きている。黒い煙の出所へ人の間を掻き分けるようにして進んで行く。その煙に近づけば近づくほどに、煙は濃く大きくなっていく。塵も火の粉がついたものが飛んでくるようになっていた。人の波の密度がさらに高まる。人々はやはりある一点を見つめている。やっとの思いで人だかりの前に出ると、冬だというのに真夏のような暑さを感じて目を見開いた。
「!」
真っ赤な炎が、割れたデパートの窓から見える。真っ黒な煙が窓や自動ドアの隙間から次々に空へ昇っていく。引っ切り無しに何かが弾けるような音や砕けるような轟音が、たち野次馬の方まで聞こえてきた。
消防隊員が必死で火元である7階の窓へと放水を続けているが、燃え上がる炎はまるで効き目が無い。火は赤く踊り狂っている。それに窓ガラスが小さな爆発で割れていくばかりだ。
「熱ッ!」
「ちゃん!」
腕に熱さを感じてがビクっと震えた。それを見てジローが庇うようにを連れて人だかりから少し離れた。それでも火の燃える音は聞こえてくる。消防隊員の指示が大声で飛び交っている。
は擦った腕を見たが、ほんの少し赤くなっただけで済んだ。
「大丈夫だよ。ありがとう、ジローくん」
「良かったCー!でも……大変なことになったね」
「うん……」
デパートは成す術も無く火が広がっていき、5階までも燃やしていった。火は勢いを増すばかりだ。しかし、自分たちにはどうしようも無い。水の力に頼るしか無いのだ。
の後ろからやって来た消防隊員が、トランシーバーで入った連絡に驚きの声を上げた。
「何だと?!まだ取り残された人があの中にいるのか?!」