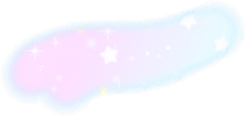
06 仲直り
教室に入って、岳人は想像していた現実とは全く違うことに唖然としていた。の席にがいた。
それは別にそこまで驚くことでは無いのかもしれない。しかし、昨日の出来事を考えると、今日は休みなのでは無いかと思っていたのだ。
廃ビルで見せたの顔。それは本当に真っ白で、血の気が無くなっていた。全ての事に絶望し、希望の欠片も無いような、そんな顔だった。岳人は初めてそんな人間の表情を見た。
もちろんに話しかけている生徒たちは、昨日にそんな出来事があったとはさらさら思っていない。それくらい、の態度はいつもと同じだった。
「本当にそんな事があったんかいな?」
「そうだぜ!オレもジローも滝も跡部も見ていたんだからな!」
昼休み、屋上で昼食を食べているときに岳人は昨日の出来事を話した。この場にいなかった宍戸、長太郎、忍足、日吉は今朝の岳人のように唖然としてしまう。それもそのはずだ。魔法を遣おうとしたなどと、普通では考えられない。日吉に至っては完全に呆れ顔だ。
「本当にそんな事があったんですか?」
「オレの話疑ってんのかよ?!」
「ええ。アンタの脳みそも疑っています」
サラッと毒を吐いた日吉に岳人が殴りかかりそうになるが、それを滝が『まぁまぁ』と制した。滝の膝には黒い漆塗りの重箱があり、純和食だった。対する宍戸やジローは購買のパンだ。ジローは滝に卵焼きをねだったので、綺麗な黄金色を1つ分けてやった。
「うん、おいCー★」
「『おいCー★』じゃねぇよ!それよかオレたちが見たことを説明するべきだろ!」
「確かに、さんは箒で空を飛ぼうとしていたよ」
「ホンマか?」
「本当にそんな事が……」
もしそれが本気なら、やはり正気を疑う。そして、岳人は滝の言葉を信じた日吉を睨みつけた。
「宗教か何かの影響でも受けている……とか?」
長太郎がうーんと唸った。
「けどよ、アイツの雰囲気からしてそんな風には見えなかったぜ?」
宍戸はのことを1度助けたことがあったが、感じの良い女の子にしか見えなかった。オカルト関係に詳しいようにも感じなかった。
「けれどね、本当に何か起きそうな……そんな予感はしたんだ」
「どういうことだよ?」
「あー確かに。それはオレも思ったぜ」
「上手く言葉には出来ないんだけどね。それに……」
滝にはのある事が引っかかっている。だが、そこまでは確信が持てない。
「そういえば、跡部は今日も修学旅行で委員会に出てるみたいやな」
「そうみたいですね」
「オレたち2年はもう今年は行ってきましたからね」
長太郎はアメリカの修学旅行の事を思い出した。このとき長太郎は修学旅行実行委員をしていたので、跡部の大変さもわかる。とは言っても、跡部は毎年この委員をやっているそうなので、長太郎の委員経験などのほんの一部にしかすぎない。
「オレたちのクラスの実行委員はなんだぜ」
「そうなんだ」
「ねぇこっちこっち!!」
「どうしたんですか、芥川先輩」
ジローは先に食べ終わってしまったのか、屋上の鉄柵に手をついて校庭の方を見ていた。サッカーをしたりバスケットをして楽しんでいる生徒たちや、ベンチで昼食を食べてお喋りをしている生徒もいる。
その中で、1人きょろきょろと辺りを見渡している少女がいた。今話題に出いているだった。ジロー以外の全員が立ち上がり、鉄柵からのことを見ている。は遠くからでも直ぐに見つかるような可愛らしい顔立ちをしていた。
しかし、妙である。
「今日って、さんは実行委員会があるんじゃ無かったっけ?」
「せやな」
「何してんだ、アイツ?」
この昼休みはの所属している修学旅行実行委員会がある時間だ。それなのに、今はこうして校庭にいる。さらに走って校舎とは反対側の中庭に向かっているようだった。今の時間ならば、もう昼食を食べ終えた生徒たちがその場を離れている頃だろう。ショートカットの髪がふわりと木陰の中に消えてしまった。
「あ……行ってしまいましたね」
「長太郎、アイツ何しに行ったと思う?」
「え?えーと……」
いきなり話題を振られた長太郎は困惑する。だが、彼が返事をする前に鐘が鳴ってしまった。校庭にいた生徒たちもざわつきながら校舎の中へと戻っていく。自分たちもここにずっといるわけにはいかない。
「オレたちも戻ろうか」
「追いかけないのー?」
「止めとき。別に悪意が無いとはいえ、女の子1人に男が寄ってたかるのはアカンで」
「ちぇー!」
ジローを宥めながら忍足は弁当箱を青い包みに仕舞った。
(本当は、ここにいない跡部が1番気にしてることやろ……)
「―――では、今日はこれで修学旅行実行委員会を終了する」
「「「お疲れ様でした」」」
跡部の掛け声で本日の委員会は終了した。今日は珍しく放課後に委員会が開かれ、教室には夕日が差し込んで赤くなっている。それぞれ委員たちは椅子を引いて多目的室を出て行く。その中にの姿は無い。残された跡部は机にある書類を丁寧にまとめていった。
と廃墟で接触してから1週間が経った。と同じクラスの岳人とジローから、が中庭付近にいるという情報を貰っていたが、あえて跡部はそれを無視していた。
跡部の手元には、真っ白の報告書が1部残されている。それにペンを走らせ、今日議題にあがっていたことを細かく書き綴った。そしてまとめ終えると針金クリップで左端を留めた。
ファイルに報告書を仕舞いこんで鞄を手に多目的室を出た。制服のポケットから鍵を取り出して扉をきっちりと閉めた。
廊下に出ると、生徒はもう校庭のどこにもいない。外はもう真っ暗に近い状態で、宵の明星が空で輝いていた。この時期3年生は引退しているうえに大会などはまだ先なため、校舎に残る生徒たちも殆どいないだろう。
薄暗い明かりの廊下を歩いていると、跡部は足を止めた。暗闇の中庭に、人影らしいものが見えたのだ。じっと目を凝らしてみれば、それはだった。は寒い秋空の下でブレザーを脱ぎ、箒に跨いでいた。
跡部は昇降口で靴を履き替えると中庭に行ってみた。やはりいたのはだった。あの日と同じように箒に跨っている。
「!」
声をかけようとして跡部は止めた。真剣に、真っ直ぐに、前を向いているのだ。教室で見せるからは信じられないほどの眼力だった。その行為自体に跡部は賛同できないとしても、の真剣さには賛同できた。
後ろに跡部がいることにも気がつかないで、は静かに目を閉じる。そして、深く息を吸い込み、深く息を吐いた。そして、もう1度目を開けたとき、再びの足元に風が吹き荒れた。渦を巻くようにグルグルとの周りを風が覆っている。しかも、以前見たときはそよ風程度だったのが、今回はもっと強い風になっている。芝がざわざわと撫でられたように揺れている。
は汗だくになって必死で箒を握り締めていた。ショートカットの茶色の髪が乱れているのも気にせずに集中し続ける。だが、やはり何も起きなかった。の集中力が切れて、肩がガックリと下がったのが見えた。
背中を向けたままこう言った。
「バカみたいだって、キミは思う?」
「……オレに気がついていたのか」
「まぁね」
は振り返って星明りの中を苦笑いを浮かべる。
「あんなに、穴が開くほど見つめられて気がつかない人なんかいないよ」
「そうか……」
跨いでいた箒から降り、はくるりと柄を下にして持った。掃き掃除には使われていない綺麗な箒だった。
「ずっとここで練習していたのか?箒で空を飛ぶ?」
「うん。廃ビルは人気が無いけれど危ないし……」
沈黙が降りる。こんな事が言いたいわけでは無いと知っていた。
がようやく口をまた開いた。
「……ごめんなさい」
一瞬、何を言われたのかわからず跡部は反応出来なかったが、一時の間をあけて、ようやく自分にが謝ったのだと跡部は理解した。は俯いたままで、表情はよくわからなかったが、おそらく笑っているだろうと思われる。
「何、謝ってんだよ」
「恥ずかしい話だけど、私……キミに嫉妬してた。何でも出来て、頭も良くて、おまけに恰好良いなんてずるいじゃない」
「ちっとも謝ってないな」
「そうね。でも、キミに嫉妬した事は間違いだった」
「何?」
先ほどまで俯いていた が顔を上げた。笑っていた。でもそれは悲しそうで、今にも消えてしまいそうな笑顔だった。
「私、魔法が遣えたの。キミには遣えない魔法を。でもね、もう遣えなくなっちゃった……」
箒の柄を握る強さがさらに加わる。必死には笑顔を作ろうとした。
「私は完璧なキミに1つだけ勝っているところがあるって思っていた。でも、もう私……何も持っていない。何も出来ない私が、完璧で何でも出来るあなたに嫉妬なんて間違いだったわ。嫉妬するのもおこがましいっていうか……」
他の魔法遣いたちは、物を宙に浮かせたり一瞬で遠い場所に移動も出来る。花を咲かせる事も富士山を巨大な大福にする事も簡単だ。
も同じ魔法遣いだが、空を飛ぶことしか出来ないのだ。ただ1つの、にとっての魔法だった。
「何も出来ないヤツに、こんな風に言われるのは嫌でしょう?だから、ごめんなさい」
跡部は頭を下げたをしばらく見つめていた。だが、その髪に手を触れると、は驚いて顔を上げた。の瞳に優しく笑う跡部が映る。そしてもう1度優しく頬に触れるのだろうと思ったのだが、予想は大きく外れる。
「痛ッ?!」
思い切りでこピンをされてしまった。痛さのあまりが涙目になって両手で額を押さえた。暗くてわからないが、絶対に赤くなっているのは間違いない。跡部は先ほどの優しい顔が、いつの間にか意地悪な笑顔に変わってしまっていた。
「バーカ。このオレ様がそう簡単に許すとでも思ったのか?あーん?」
が今度は怒る番だった。額を押さえたまま睨みつけるが、跡部はお構いなしだ。1度に視線を合わせ星を見上げた。
「お前は本当に何も出来ないのか?」
「え……」
「もう何も出来ないなら、何であんな事してたんだ?」
魔法の練習のことを指していることに気がついて黙る。
「何も無いなら、練習とかしても仕方がねぇだろ」
「だけど……」
「お前が諦めていない何よりの証拠じゃねぇの?違うか?」
「わ、私……」
どうして何も持っていないなら練習などしていたのだろうか。は手が肉刺だらけになるまでずっと箒を握り締めてきたことに気がついた。
だって、だって
本当は……
「それで、仲直りはできたのかよ?」
「「!?」」
と跡部がその声に驚いて振り返る。氷帝テニス部を任された長太郎と日吉、そして後輩の指導をしていた元テニス部レギュラーのメンバーがいた。こんな時間にこんな場所で出会うとは思ってもみなかった。
最初に声をかけた宍戸が帽子を被り直す。あっけに取られてぼーっとしているだったが、跡部だけは彼らの登場に驚く素振りは見せなかった。
「余計な事してんじゃねぇよ」
そうは言う跡部だったが、その顔は迷惑そうには見えなかった。ジローはにこにこと笑っている。
「今日跡部がこっちに来なかったのって、ちゃんの分の報告書もまとめてたからでしょー?」
「え……?」
「やることは意外とマメだよな〜」
「そうですよね。そんな風には見えませんが」
「ひ、日吉?!」
長太郎は、日吉の毒付いた言葉を慌ててかき消そうとしたが遅かった。跡部は指摘されて特に何も反応すること無く、鞄のファイルからの分の委員会の報告書を取り出した。そこには綺麗な文字が並んでいる。
「跡部くん、ありがとう……」
「礼を言うなら今度からは委員会に出ろ。これ以上面倒をかけるな」
ぶっきらぼうだったが、肩の力がスッと消えた気がした。
「何だかんだで跡部のヤツ、ちゃんのこと気にしてたんやな」
「ですね」
「とりあえず、仲良くなったのならめでたしめでたしだねー!!」
ジローはお気楽に笑っていた。その声に反応して、生徒指導の教師が窓から顔を出す。キョロキョロと自分たちのような生徒が残っていないか探しているらしい。
「皆、こっちから行くよ」
滝の機転により、を含めた彼らは裏口からこっそりと薄暗くなった空の元で帰り道を急いだ。秋空の冷たい風が吹き、制服の下にも進入してくる。冷たく震えていたが、どこか温かい気がしていた。
明かりの灯った街中に入ると、人混みに何度も押されそうになってしまう。ふと、が顔を上げてみると、真っ白に輝いたビルとビルの隙間からあの廃ビルの屋上がほんの少しだけ見える。
そして、ゆらり、と視界に入ったのは人影。
「あそこ、誰かいる……!」
「こんな夜に?」
滝も足を止め、結果彼ら全員も足を止めてと同じ方向を見た。確かに、ぼんやりとではあるが、誰かが立っている。それは小さな子供のようにも見えた。
なぜだか嫌な予感がして、は廃ビルに向かって走り出していた。