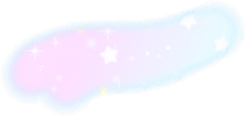
03 噂の転校生
都内のとある魔法士事務所で、は卒業試験の結果を待っていた。目の前に座っているこの事務所の魔法士は、難しそうな顔で結果を告げた。「……残念だけれど、結果は不合格です」
「?!」
覚悟していたとはいえ、は冷や水を浴びせられたように背筋が凍った。僅かでも希望を失わなかった事で、余計に胸が抉られてしまう。
魔法士は気の毒そうにを見つめる。
「魔法士の中には、その能力に偏りがある人もいる。けれど、キミの場合はその偏りが極端過ぎるんだ。キミの魔法は、物体浮遊の魔法……。しかし、浮かせられるのはキミ自身だけ。しかも、箒に跨らないと遣えない……」
「…………はい」
卒業試験の課題は、依頼主の引っ越しの手伝いをするという、卒業試験にしては簡単なものだった。重い荷物を魔法で浮かせ、引っ越しを短時間で済ませる。下手をすれば、普通の人間にも出来る試験だ。
しかし、は魔法で荷物を浮かせようとしたが、荷物は微動だにしなかった。それどころか、1枚の紙すら浮遊させる事が出来ず、試験は結局失敗に終わったのである。
は泣きそうになるのを耐え、必死で魔法士に訴えた。
「私は、一般人ではありません!魔法が遣えるんです!私は、魔法遣いです!」
「それはわかっているよ。でも、魔法が遣えるだけでは、魔法遣いにはなれても公認魔法士にはなれないんだ。キミも理解しているだろう?」
「!」
「公認魔法士は、依頼人の依頼を達成してこそのものだ。依頼人を満足させられなければ、公認魔法士にはなれない」
「…………」
は拳を握り、俯く。これ以上何を言っても、この結果は覆らないと悟ったのだ。
「キミはずっと努力してきたと聞いている。研修中も、頑張っている姿は私も見てきた。けれどね、現実はそこまで優しくないときもあるんだよ」
「だけど、私は公認魔法士にならなくてはいけないんです!父だってそれを望んでいるはずです!祖母のようにならなければ、私は……っ私は、何も出来ない人間になってしまうんです」
ずっと抱いてきた劣等感が一気に噴き出した。
空を飛ぶ事しか出来ない魔法遣いが自分の存在を認めるためには、他に方法が無い。
魔法士は諭すように言った。
「ちゃん、キミのお祖母様―――先代の魔法局局長は本当に偉大な人だ。だからって、孫であるキミが公認魔法士になる必要は無いんじゃないかな?努力で全てが上手くいくわけじゃない。それはキミ自身が良くわかっているはずだろう?」
の口の中はカラカラに乾き、唾を飲む事も出来ず茫然とした。
にとって、これ以上重い言葉は無い。押し潰されてしまいそうな感覚を覚え、は青ざめた顔をゆっくりと上げた。
か細く消えそうな声を絞り出す。
「先生……、私は、いったい何のために魔法が遣えるんでしょうね……」
「ちゃん……」
ポロポロと両目から涙が零れ落ちる。苦しそうに自虐的な笑みを浮かべて、は唇を震わせた。
「公認魔法士になれないのなら、魔法、なんて……もう……この世から、消えてしまえば良いのに……!」
これは、が大怪我をする1週間前の出来事である。
電車通学を始めるようになって2週間目。ぎゅうぎゅうに押さえつけられる電車は、どうしても怪我に響く。
は今、祖母が使っていた空っぽの事務所で生活している。不便なことは何も無い。これまでずっと1人で暮らしてきていたから。。
(本当に、この世界はどうなっちゃったんだろう……)
魔法遣いたちを監理している魔法局本部にも行ってみた。けれど、魔法局など無いどころか、魔法そのものが人々の暮らしの中から消えてしまっていた。魔法は、どうやらこの世界では御伽話にしか過ぎないようだ。
誰も信じない魔法を、自分は遣える。ある意味それはの望んでいた世界。
(怪我が治ったら、まず魔法を遣ってみよう)
は目的の駅に着くと、人並みを必死で避けながら歩いた。
とりあえずは普通に学校へ行く。そうすることで、混乱する自分を守ることに繋がっていた。
「きゃっ?!」
改札口に近づいたとき、前から急ぎ足でやって来たサラリーマンに、避ける間もなく突き飛ばされてしまった。膝の怪我は完治していただったが、まだ腕を骨折しており固定してある。受身を取れず、体が傾くのを感じて目を閉じた。
そのときだ。全速力で走ってくるような足音が響いて、背中はコンクリートの硬さではなく人の温もりを感じた。ぎゅっと瞑っていた目を開ければ、そこには帽子を被ったキツい目つきの少年がいた。よく見れば、自分と同じ学園の基準服を着ている。
「おいおい、大丈夫かよ?」
背中にはいつの間にか彼の腕が回されており、なんとか倒れずに済んだ。
が声を上げる前に、少年の方が先に反応した。
「ん?おまえ転校生のじゃないか」
「キミは、誰……?」
「ああ、オレは隣のクラスの宍戸亮だ」
宍戸はそう言ってをきちんとした姿勢に立たせる。
宍戸亮。どこかで聞いたことがあったような気がした。転校初日に、テニス部について熱く語っていたミーハーな女子生徒が言っていたのを思い出す。その中に登場してきた名前だ。
と宍戸は人の流れの激しくない端の方へ寄った。
「助けてくれてありがとう。朝の通学電車って本当に大変なのね」
「何だ、お前は今まで電車通学したことなかったのかよ?」
「う、うん……」
は鞄を持ち直して宍戸と駅を出た。
「ごめんね、鞄まで持ってもらっちゃって」
「別にかまわねぇよ。それよりあまり腕に負荷をかけるな。傷が治るのが遅くなるぜ?」
「うん。ありがとう」
「特に行きと帰りの電車には気をつけな。あー、こんなときに魔法でも遣えたらなぁー」
「えっ?!魔法?!」
いきなりこの単語が出るとは思わなかった歩みは思わず反応してしまう。
「ん?ああ、冗談だよ冗談」
「そっか……そうだよね、あはははは!」
宍戸は変な顔をしてを見たが、は笑ってその場を誤魔化した。
今1番魔法を必要としているのは宍戸ではなく、の方だった。
「そういえば、宍戸くん私から結構離れたところにいたよね?なのに、直ぐにこっちに来て私を助けてくれたでしょ?足が速いんだ?」
「ああ、足の速さには自信があるぜ。今は引退したとはいえ、テニス部だったからな」
「そうなんだ。すごいね」
はにっこりと微笑んだ。
先ほどの宍戸の足の速さは本当にすごかったのだ。まさに、一瞬で移動してきたのかと思わずにはいられない。常人ではとてもマネできないことだろう。
宍戸は照れた様子で額を人差し指で掻いた。
「別にそんなことねぇよ。誰だって、練習さえすれば出来るようになるぜ」
「そう……だね……」
の表情急に暗くなる。
「おい?どうした?」
「え?」
「顔色悪いぞ?人に酔ったか?」
「そんな事無い、平気平気」
慌てては笑って見せた。宍戸は変な顔をしたが、再び歩き出した。
(『練習していれば出来るようになる』。私もそんな風に考えていた事があったな……)
は満たされない気持ちを抑えつけるように地を蹴った。
氷帝テニス部は部長も引退し、新人戦も終えて一段落がついた頃合だった。だが、テニスの名門である以上、今日も毎日練習はかかさない。放課後のテニス部は引退した3年生の分を補うようにと、以前よりも遥かに気合が入っていた。
特に跡部という輝かしい頂点を失い、それを引き継いだ日吉と長太郎や樺地は部員の中でも一際練習に励んでいた。
校庭の走りこみが終わり、日吉と長太郎は肩で息をしながらベンチに座った。1年生部員が用意してくれていたスポーツドリンクを飲み、息を荒く吐く。
「はぁ、はぁ……。日吉、また随分と早いペースで走ってたな」
「はぁ……はぁ……。おまえこそ、そのオレによくついてきてるぜ」
「跡部さんに任せられた者同士、頑張らないといけないし……」
そう言って、また長太郎は残り全部のドリンクを飲み干していく。
もう涼しい風が吹く時期だが、身体の方は真夏のように熱く火照っている。日吉もタオルで汗を拭った。
「お前はダブルス向けの選手で、宍戸先輩と今まで組んでたが、またダブルスで攻めるのか?」
「いや、今までは宍戸さんに頼りっぱなしだったけれど、今度からはシングルスでも引けをとらないようになりたいって思ってる」
「へぇ……」
「それに、宍戸さんにだって勝てるようになりたいしね!」
力強くそう言い切った長太郎に、いきなり後ろからスポーツタオルが投げられた。突然の襲撃に長太郎は驚き、視界を遮ったタオルを剥ぎ取る。振り返ると、投げたのは噂の人物だった。
「オレが引退してから、随分と大口叩けるようになったじゃねぇか」
「うわ?!し、宍戸さん!?」
「どうも」
日吉は相変わらず愛想の無い返事をしてみせる。宍戸がその様子に笑った。その後ろからは、かつてのダブルス名コンビである忍足と岳人もいた。
「引退したっていうのに、アンタ方はいつまでも先輩面ですか」
「そう言うなや。引退後にも後輩の面倒は見なくちゃアカンやろ」
「そうだぜ!OBとして顔出すのも先輩の役目なんだぜ!」
向こうでは、跡部が2年生に囲まれて何やら指導をしている。それよりも、応援に来ている女生徒たちの視線や黄色い悲鳴の方が目立っていた。日吉は苦い顔、長太郎は困ったように笑っている。
「何だか先輩たち、全然引退したって感じしませんよね」
「ま、受験つっても外部希望者以外はエスカレーター式だからな。あまりその辺は心配してねぇんだよ」
あまり得意げに話しているので、日吉はあることを思い出してニヤッと笑った。
「そうえいば宍戸先輩、今朝は女連れで登校したんですよね?」
「なっ?!」
「あー知ってる知ってる。けっこう有名になってるぜ?」
「せやなぁ。オレも今朝聞いたで?」
「いったい誰がんなことを……?!」
宍戸は顔を赤くさせて怒った。とは言っても、照れているだけの事をその場の全員が知っているので、全く悪びれる素振りは見せない。むしろニヤニヤと貶める気満々の表情だ。
長太郎だけがその話を知らなかったらしく、目を丸くさせて驚いている。
「ええ?!そうなんですか?宍戸さん、おめでとうございます」
「何を勘違いしてんだよ!!別にそんなんじゃねぇ!」
これ以上の誤解を避けるため、宍戸は今朝駅でよろけたを助けたことをざっと説明した。聞いている側は興味津々の様子である。
「それはロマンスやなぁ」
「ロマンスなわけねぇだろ!」
「先輩……。そういえば聞いたことがありますね」
「お、2年の日吉も知ってるのか。侑士の言うようなロマンスっていうより、大怪我しててしかもこの時期に転校してきたっていうのがあるからな。有名になって当然なのかもな」
「もしかして、向日先輩たちのクラスなんですか?」
「そうだぜ?な、侑士」
「そうやで。めっちゃかわええ女の子やし、クラスの男子がみんな狙ってるんとちゃうか?」
包帯がぐるぐるに巻かれた転校生というのは、やはりどこでも注目されるもののようだ。それに可愛らしい容姿も手伝っている。
は、東京に来る以前の話について尋ねられるとあまり話したがらない。それを見て、に対する好奇心は益々高まってしまっているようだ。
「そういえば、今日は滝先輩見かけてませんね」
「滝は実家のお茶会の手伝いがあるんだとよ」
滝家では華道と茶道の家元を同時にこなしているため、ときどき滝自らが部活を休んで手伝うことがあった。
そのまま雑談をした後、引退した3年の指導を受けながら氷帝テニス部は今日も忙しく部活に励んだ。
定期検査のために病院から出たは、家路へと急いでいた。スマホをいじりながら今日の分の食材を買っていないことに気がつき、途中で街中に戻った。
夕方であるため、スーパーには献立を紺が得る主婦で賑わっていた。野菜コーナーに立ち寄り、カレーのルーが安くなっているのを見て、今日はカレーにすることにした。
(カレーって冷凍庫に入れておくとけっこう保存できるのよね……)
すっかり主婦モードにチェンジされたは、袋に買った食材を詰め込んでスーパーを後にする。もう太陽は殆どビルの谷間から消えてしまっていた。
道を歩く人々は主婦から学生やサラリーマンなどに変わり、東京の街は明るく照らされ出す。それは昼間よりも眩しいとさえ感じるネオンの光りだった。
横断歩道を渡り、は重いスーパーの袋と鞄を片手に持って歩道橋の階段を上って行った。
(何だかこの歩道橋古いみたい)
足元を見れば、暗がりの中ひび割れたコンクリートが見える。ビルやマンションはすぐに建てられるが、歩道橋などは相変わらずそのまま放置されているようだった。
せっせと上がっていくと、ようやく1番上の段を上りきる。丁度そのときだった。歩道橋の1番下の段に、季節の花を両手に抱えた滝がやって来た。床の間に飾る花を得意先に注文してあったものを、学校帰りのついでに取りに行っていたのである。優しげな香りが滝を包んだ。
「後はもう用事無いな」
2段目に足を伸ばしたとき、突然冷たい風が吹いた。それもかなりの突風。滝は驚いて花を護るように抱き締める。
コツっとローファーを踏み外すような音が響いて、滝は顔を上げた。すると、1番上にいた同じ基準服姿の少女が先ほどの突風にバランスを崩している。片手に持っていたスーパーの袋と鞄がするっと手から離れ、怪我をして固定されている右手が大きく揺れた。あっという間に足をそのまま宙に投げ出してしまった。
「きゃあっ!?」
恐怖が滲んだ悲鳴が聞こえ、少女――― は背中から後ろに落ちていく。咄嗟に滝は、持っていた花束をコンクリートに投げ捨てて階段を一気に駆け上がる。間一髪のところでの背中を抱きとめた。だが、それだけでは衝撃の勢いは殺しきれない。滝は支えきることができず、自分も階段から足を踏み外してしまった。
「うあっ?!」
嫌な浮遊感が一瞬だけ自分たちの体を支配する。現場を見ていた人々も異変に気がつき、悲鳴を上げた。
滝とはぎゅっと目を瞑り、そのときが来るのを待った。コンクリートに背中から滝は着地してしまう。さっき滝が投げ捨てた花が、その辺に散乱して花吹雪になってしまっている。
は着地したことがわかると、すぐに滝から離れた。そして周りを見て自分がしてしまった事に青ざめる。
「ごめんなさい!!怪我、してますか!?」
しかし、滝は心配するの姿が見えていないのか、茫然としてしまった。
(今、何だかおかしくなかったか……?)
一瞬感じた違和感に、滝は困惑していた。しかし、ようやくの声に反応して頷く。
「あ、ああ……。キミこそ大丈夫かい?」
「背中痛みますよね?!本当にごめんなさい……!!」
は滝の傍で泣きそうな顔になってしまっている。
現場を目撃していた人の1人が救急車を呼ぶ。滝は上半身を起こして背中を摩った。
花は飛び散ったままで、歩道橋の階段から人が落ちているとあって、2人の周りには人だかりが出来てしまった。
その間を受け止めて落ちた滝は、痛そうというよりも不思議そうな顔をしているだけであった。
感じているこの違和感が、今後大きな意味を持つことになるとは、まだ誰も予想出来なかった。