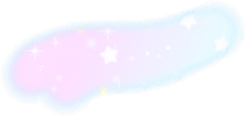
02 魔法が消えた世界
いったいどういうことなのだろう、とは思った。けれど、今はとりあえず微笑むように心がける。今日からの担任教師となったメガネの彼は、ハキハキとした声での事を生徒たちに紹介した。
「今日からキミたちのクラスメイトになるさんだ。彼女は日本生まれだが、お祖母さんの考えもあって、イギリスの郊外で暮らしていたそうだ。日本に戻るのはこれが初めてだったな?」
「え……、あ、はい!」
いきなり話を戻されたは、少しばかり動揺しつつも大きく首を縦に振った。それと同時に、生徒たちから『帰国子女だってー!』や『跡部と同じだな』などという反応が返ってきた。氷帝学園ほどの大きな学校ならば、帰国子女くらい珍しく無いものと思っていたが、そうでも無いらしい。所詮は中学生だ。自分の経験には無い事に反応してしまう。特に『外国で暮らしていた』、というキーワードは彼らにとって憧れの対象以外の何ものでもない。
「日本語はお祖母さんに?」
「はい。家では日本語で会話していましたから……。不自由はありません」
「それにしても酷い怪我だなー、キミ。初日から無理はするなよ?」
担任教師が顔をしかめての怪我した部分を見た。
は頭を包帯で、右目をガーゼで覆っている。そして、右腕はギプスを包帯ぐるぐる巻きして三角巾で固定されていた。さらに、左腕はギプスはしていなかったが、こちらもぐるぐる巻きになっており、とても痛々しい。そして、両膝はガーゼで傷が覆い隠されている状態だ。つまり、満身創痍。
帰国子女というだけでなく、大怪我までしている謎の転校生とでも は思われているに違いない。生徒たちは、好奇心旺盛な目でをじっくり観察していた。
「大丈夫です。本当に、大丈夫ですから」
は教壇の前でなんとか笑うと、生徒たちにショートカットの頭を下げた。顔を上げて自己紹介をする。
「初めまして、です」
初めまして?本当にこんなこと初めてだ。
「イギリスで暮らしていたせいか、この東京にはちょっと不慣れです……」
そう、イギリスで生活していた事。それから、飛行機に乗り、東京に向かっていたところまでは覚えている。
「氷帝学園は、私の祖母も実は通っていました」
でも……、ここはお祖母様の通っていた氷帝学園じゃない。
「ええっと……好きな食べ物は甘いもので、特技は―――」
私の、特技は、
「……ん?どうしたんだ?」
黙ってしまったに注目が集まり、ハッとなる。一気に現実に引き戻され、は言いかけた言葉を飲み込み、別の言葉を吐く。
「特技は、これといってありません……」
大怪我をしたままの帰国子女は、あっという間に生徒たちの渦の中心へ。目が白黒してしまうような質問攻めに、は別の意味で頭が痛くなった。四六時中質問攻めに合い、休まるときが無かったは、結局気分が悪いとして午後は保健室で過ごした。保健室の先生は初老の女性と思われる人で、はふいに祖母の姿を重ねる。
「あらあら、それは大変だったわねぇ」
事情を説明すると保険医はニコニコとしながらにベッドを進めてくれた。しかし、横になるような気分では無いため、はベッドに腰を掛ける。外はまだ残暑が厳しく、日差しが強く窓から入ってきていた。クーラーからの送風が頬をくすぐる。
保険医は、ガラスのコップに自分の分との分の麦茶を入れて、片方をに手渡した。はまだ自由の利く左手で器用にコップを受け取った。
「それにしても大怪我みたいじゃないの。いったいどうして?」
おっとりとした口調で訊ねられるが、は人には到底説明できない出来事でこうなってしまった。
話せない。
少なくても、この世界の人には。
「ちょっと階段で転んじゃっただけですから。それに、転校初日から学校休みたくなったんです」
「そうなのそうなの。元気で良いわねぇ」
「ええ……。まぁ……」
は曖昧な返事しかできなかった。のこげ茶色の瞳が伏せられていく。
どうしてこんなことになってしまったのだろうか?少しでも油断すると、気が狂ってしまいそうになる衝動を必死で抑えた。
コップを隣にあったチェストに起き、制服のポケットからは小さな指輪を取り出した。飾りの石は透明で楕円、溶けるような淡いオレンジ色をしている。
「それはなぁに?あなたの?」
「いえ……これは、私の祖母の指輪なんです」
「そう、あなたのお祖母さんのねぇ」
「はい」
ぎゅっと握り締める。金色の輪が指の間から輝きを放っているのを、はじっと見つめた。
これはの、半年前に亡くなった祖母の形見。
それと同時に、政府公認の魔法遣いの証となる指輪だ。
魔法遣い。
それは、風や火、水をいとも簡単に生み出し、ときには地球の裏側へも瞬間移動出来る人。それが彼ら魔法遣い。彼らは公務員で、国に監理される存在だ。魔法遣いたちの正式名は【公認魔法士】である。そして、公認魔法士たちには公認である証の指輪が支給される。
日本では、日本国籍を持つ魔法遣いたちの支援、魔法労務の遂行及び統括を主な目的として、内閣府の外局として魔法労務統括局が発足された。そこでは国内全ての魔法遣いたちの動向を把握し、管理している。通称名は【魔法局】。魔法局は各地方自治体に存在し、一般人からの魔法の依頼を受けている。立派な公的機関の1つである。
基本的に公認魔法士は国家に所属し、研修を受けて合格し、免許を持たなければならない。無所属及び無免許での魔法使用は違法であり、刑法によって罰せられる。
また潜在的に弱い魔法力を持ちながら遣わない者、弱すぎて遣えない者や、無免許で魔法依頼を受ける【ハグレ】と呼ばれる魔法遣いも存在する。
それが、の知る世界。
魔法は存在するが、テレビも携帯電話もパソコンもある。車もガソリンで走っている。電車や飛行機だって、科学の力で動いている。ただ身の回りに魔法遣いがいて、正式な手続きさえ取れば、誰でも公認魔法士に魔法を依頼することが出来るという仕組みだ。
保健室で一眠りしたは、放課後の廊下を1人歩きながら窓の外を見た。スカイツリーが見える。夕日がさらに聳え立つそれを赤く染め上げていく。
あの空を、つい最近まで飛んでいた。は、魔法の力で飛んでいたのだ。
天まで届きそうなスカイツリー。
暗い裏路地。
忙しく歩き回るサラリーマンの群れ。
クラクションを鳴らす車。
友人とお喋りを楽しむ学生。
空の色。
太陽の眩しさ。
アスファルトの隙間に生える雑草。
全てが、同じだと思っていた。
けれど、ただ1つだけ違うところがある。
この東京には……、
あるべき魔法が無い。
まるで、最初から存在しなかったように。