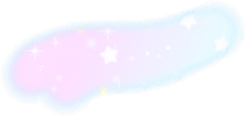
01 最期の言葉
例えば、『死んでも良いと思うのはどんなときですか?』という質問をされたとして。その問いに、『自分が死んで世界が滅ぶなら、喜んで死にましょう』と、私は答えるのです。
今、マンモス校として有名な氷帝学園の敷地内には、平日にも関わらず誰1人いない。巨大な敷地は、もはや入れる物の無い空箱になっていた。この日は特に開港記念日でも何でもないにも関わらず、生徒はもちろんのこと、職員たちも全員いない。さらに付け加えるなら、学園から半径1キロ以内には住民さえ見当たらない。人影の無い町内。まるでゴーストタウンのようだ。
もちろんのこと、これは人為的に行われたものである。事柄の指示者である日吉は、同級生の長太郎と樺地、そして学園の校門前に数名の教師たちと待機していた。手には白のスマホが握られている。次の連絡を待つためだ。
スマホが振動を掌に伝えた。長太郎は大きな手を器用に扱いスマホを開く。液晶の画面に出たのは非通知表示の番号。しかし、日吉は迷わずアイコンを素早くタップした。相手が誰であるのかは、もうわかっている。
『もう学園内には誰もいねぇだろうな?』
「ええ、跡部さん」
電話の相手―――跡部の声は、いつになく低く感じた。
『近所の住民は?』
「いません。指示に従って、今は安全な場所で待機してもらっています」
『そうか……』
安心したような声。とても優しく日吉の耳に届いた。しかし、状況がさっぱり読み込めない。
「跡部さん、いったいどういうことなんですか?」
『残念だが、時間がねぇ。質問には答えられない』
「なぜです?」
『良いからお前はオレ様の指示に従って、お前も住民たちと同じところへ移動しろ。わかったな』
「……納得出来ません」
電話の向こうで溜め息が聞こえてきた。別に呆れているという雰囲気では無い。すると別の声が出た。
『日吉、わかってやりや。オレたちもう時間無いねんて』
おっとりとした関西弁が、少しだけ懐かしい。
「それが、どういう意味だか聞いているんじゃないですか」
『…………』
沈黙。短くて、長い沈黙だった。静かで、いつもと変らない忍足の声だったが、日吉にはそれが不安で溜まらない。
何かが、向こうで起きている。
大きな何かが、起きている。
「日吉、オレと代わってくれ」
振り返ると真剣な眼差しで、長太郎が手を差し出していた。日吉は何も言わず、スマホを投げて寄越した。長太郎はそれを素早く受け取ると、自分の耳に押し付けた。
「先輩、オレたちできるだけの事はします。力になります。だから、教えてください」
『……あかん』
「先輩!!」
長太郎が声を荒げるなど珍しいことだったが、忍足は何も答えなかった。沈黙が少しだけ流れて、それからまた違う声が聞こえてきた。
『長太郎』
「宍戸さん……?!」
自分が最も世話になった先輩の声に、長太郎は驚く。宍戸はいつになく落ち着いた口調で言った。1つ1つを確かめるように。
『お前、テニスは好きか?』
「も、もちろんです!」
『なら、お前と日吉、樺地で話し合って次期部長を決めろ。オレたちは、お前ら3人なら誰がなっても構わねぇって思っている』
突然のテニス部次期部長の話に長太郎は混乱していた。それでも話は続く。次に電話に出たのは岳人だった。おちゃらけた彼の声も、やはり重かった。
『前から考えてたことだからよ……。それに、今伝えなくちゃ、もう………言えねぇ、から』
最後の方はほとんど泣いているようにか細く聞こえた。岳人の元気な様子はこの声からは伺えない。
『こっちはオレたちが何とかする。絶対に……食い止めてみせる』
「滝先輩……」
『ああそれと、オレたちの家族に、愛してるって、伝えてくれよな』
「ジロー先輩……!」
『よろしゅう頼むで』
「忍足先輩!!」
遮るように声を荒げた。何を覚悟しているのだろうか。それは、言わずともわかったが、それでも長太郎は口にせずにはいられない。
「何を……何を言っているんですか?」
声が震える。
「これじゃあまるで……ッ、……先輩たちが―――」
搾り出す。
「これから、死ぬみたいじゃないですか……!」
長太郎の言葉に、日吉も樺地も目を見開いて反応した。
自然と涙が出そうになる。不安で仕方が無い。
何も状況が読めてこないのに、その事だけははっきりとわかっていて……。
跡部に声が代わった。
それは、笑っているかのように。重さなど無い、いつもどおりの声だ。
『鳳』
「……は、い」
上手く返事ができただろうか。そんなことを考えながら、次の言葉を待った。
『迷惑を、かけたな。すまない』
らしくない。普段の跡部とは到底思えない言葉だった。
「跡部先輩、本当にどうしたんですか?!」
ここで、長太郎は大きなことに気がついた。
先ほどまで電話に出た人物。跡部、忍足、岳人、宍戸、ジロー、滝。
足りない。
髪の短い、優しくも悲しく笑う少女の顔が浮かぶ。
「先輩は……、先輩はどうしたんですか?!」
向こうで息を呑む音がした。
沈黙の後、跡部は息をもう1度吸い込んだ。
『は、もう―――』
そこで電話はブツリと途切れた。
握り締めたスマホ。
顔面蒼白。血の気が引いていく。
最後に、長太郎の耳に届いたのは、誰かの悲鳴と、割れんばかりの大きな音。
それは、確かに―――
銃声だった。