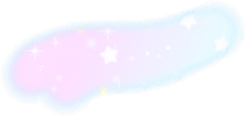
11 クローバー
の携帯のディスプレイに表示されている名前を見て驚いた。それは日本にいる長太郎からの電話だったのだ。一瞬迷ったが、とりあえず受話ボタンを押して『もしもし?』と呼びかけた。すると長太郎の落ち着いたトーンの声が耳に入ってくる。『あ?もしもし、先輩ですか?いきなり電話しちゃってすみません。今お時間大丈夫ですか?』
「う、うん、平気だよ。ところでどうしたの?」
いっぺんに色々な事があったせいで動揺していただったが、平常心を装って聞いてみる。日本からわざわざイギリスまで電話してくるなど、よほどのことだろうと思ったのだ。
『先輩、出発前になんだか元気が無かった気がしたので……』
は『え?』と声を漏らした。出発前のは、誰に対しても笑顔を絶やさなかったというのに、その奥に秘められた部分を長太郎は読み取ったのだろうか。は少し間を空けて問う。
「どうしてそう思うの?」
『……ということは、やっぱり落ち込んでいたんですね』
「う……」
長太郎の顔はきっと苦笑いを浮かべていると想像できた。
『でも、仕方ないですよ。あんな事があったんですし……』
助けたはずの小学生の自殺、火事で亡くなった人たち。魔法を遣って、初めて役に立てたと思っていたことが、全て裏目に出てしまった。魔法には強い信念を持つにとって、それはショック以外の何物でもない。
はようやくここで自分の気持ちを隠さずに言葉に出来た。
「私……、もうダメだよ……」
『先輩?』
唇を噛み締めながらは言葉を紡ぐ。
「魔法遣いのくせに魔法だってちゃんと遣えなくて、それなのに偉そうなことばっかり……。私、本当にバカみたい。皆が優しいことに甘えてさ……。裏切ってばっかりだよ……!」
電話越しに長太郎が息を呑む音が耳に伝わってきた。呆れられてしまったかと思った瞬間、長太郎の口から出たのは意外な言葉だった。
『オレたちは……』
「?」
『オレたちは、少なくても先輩が魔法遣いだったから近づいたわけじゃありません』
「ご、ごめん……」
はもう泣きそうだったが、それでもさらに唇を噛み締めて声を出さないように必死だった。だが、長太郎にはわかっているらしく、優しく語り掛けるように芯のこもった声で言った。
『先輩、思い出してください。オレ、先輩たちから聞きました。先輩が火事の中に飛び込んで行ったとき、誰も止めなかったって。それがどういう事なのか、わかりませんか?』
「え……?」
は火事の後で病院に運ばれている。その間のことは何も知らない。
『あの人たちが何を信じていたと思うんです?魔法じゃありません。あなたです。あなたを信じていたんです』
『結果とか、そういうことじゃないんです。あなたのしようとする事や、あなたの言葉を信じていたんですよ』
『先輩、あなたはあのとき何を信じていましたか?』
『あのとき、あなたを【魔法遣い】にしたのはいったい何か、思い出してください』
はもう我慢出来ず涙を零していた。
この言葉では全てを知った。自分が出来そこないの魔法遣いだからショックを受けていたわけでは無い。は、期待をしてくれていた彼らの役に立てなかったことが辛く、とても悲しかったのだ。
の中にあったわだかまりが、全部溶けて無くなっていくのを感じた。
急に黙ってしまったを、心配そうに長太郎が問いかけた。
『先輩……?大丈夫ですか?オレ、余計なことを言って……』
「ううん、そんな事ない。ありがとう」
『そうですか、良かった。先輩が元気になったみたいでオレも嬉しいです』
「心配かけちゃったみたいでごめんね!でも、私はもう大丈夫だから」
長太郎との電話後、は祖母の残した手紙を持ってホテルへと戻ることにした。気がつけば夕方で、は慌てて走り出した。
もうには重くて冷たい壁が消えていた。あるのは希望という小さな光。はようやくそれを見つける事が出来た。
一方、日本でこんな会話をしていることをは知らない。
「先輩、元気になったみたいだよ」
「そうか」
「それにしても……」
「何だよ?」
鋭い目つきの日吉に長太郎は笑顔で言った。
「良くわかったな、日吉。菊池先輩が元気無いってこと」
「別に……。いつになく笑ってたから気になっただけだ」
照れ隠しを知っている長太郎は、睨まれても特に気に留めなかった。その様子に『けっ!』と悪態をつき、日吉は両腕を頭の後ろで組む。
「電話しようって提案したのはお前だろうが」
「まぁそうだけど。日吉はもっと素直になりなよ」
「うるさい黙れ」
「あははは。だけど、ちょっと気になるな……」
「何がだ?」
考え込むような仕草を見せる長太郎に日吉は問う。
「話す前の先輩、なんだかちょっと様子が変だったんだ。向こうで何かあったのかもしれない……」
くるりと日吉が背中を向ける。
「別に大丈夫だろ」
「え?」
「あの人たちも一緒だからな」
「ああ、そうだね」
「あの人たちなら、きっと上手くやるだろう」
3泊4日というイギリス修学旅行はあっという間に終わりを迎え、いよいよ4日目の帰国の日となった。ホテルの部屋で荷物をまとめ、は跡部財閥の管理している空港へと向かった。
結局長太郎との電話後、はケンカをしてしまった彼らと話す機会を見つけられなかった。あのような物言いをしてしまっては当然なのかもしれないが、それは彼らも同じ。それに、自由時間にはずっと彼らはどこかへ連れ立って出かけていたのだ。その行き先は全くわからず、はその間もずっといつ謝罪をしようかと考え込んでいた。
(私が悪いんだから……。けど、いつ謝れば良いかわからないなぁ……)
空港はとても大きく、またしても跡部財閥の力を見せ付けられる。跡部は氷帝学園の一行を全員収容できるだけの大きな飛行機をこの日のために製作していた。それは氷帝学園専用と言っても良い。行きもこれに乗って来たわけだが、機内も豪華でやたらと派手だ。もうこの感覚に慣れてしまうと、普通の機内がむしろおかしく思えてしまう。
(行きも帰りも同じ……ってことはつまり……!)
そう、行きと帰りが同じ飛行機ということは、座席も行きと同じという事になる。の席の隣には岳人が座るのだ。
跡部財閥のフライトアテンダントが生徒たちを席に案内し、が自分の席へ移動するとそこには既に岳人が座っていた。岳人はと視線が合えば、ハッという顔になってバツが悪そうに顔を背けてしまった。さすがにこれにはも堪えた。しかし、自分が悪かったのだとしゅんとして自分の席に座った。
「お客様にお知らせ致します。間もなく当機は空港を飛び立ちますので、シートベルトをしっかりとしてください。なお、離陸中は安全のため、決して席をお立ちにならないようお願い申し上げます」
丁寧なアナウンスが流れ、飛行機は轟音と共にイギリスの地を飛び去った。窓から見えるイギリスの街並みは、みるみるうちに遠く小さくなっていった。は窓からその様子を眺めながら溜め息をついた。
(気まずいなぁ)
隣に座っている岳人は、さっきから一言も発しないのだ。行きの飛行機の中では元気良くはしゃいでいたのが嘘のように。ただ黙って前を向いて座っている。
「おい」
「!」
突然、前を向いたままの岳人に声をかけられて、は驚き振り向く。岳人は初めての顔を自分から見つめ、そして手を差し出した。握られた手を差し出され、は何も察せず混乱した。
「何ぼさっとしてんだよ。手を出せ」
「え?あ、うん……」
「ほら、やるよ」
いきなりではあったが、は岳人に片手を差し出した。すると岳人の拳に握られていた手か開かれ、そこから小さな光るものが落ちた。その光るものはの掌へ着地した。見ればそれは小さな銀のクローバーがついた指輪だった。小ぶりで愛らしい、年頃の少女に似合うものだった。はスカートのポケットに入っている祖母の形見であり、公認魔法士の証である指輪を思い出す。その指輪よりもには丁度良い。
驚いた顔で指輪を見つめるは岳人を見た。岳人の頬は少しだけ赤かった。
「これ、どうしたの?」
不思議そうにが問うと、岳人はぶっきらぼうに言った。
「魔法遣いは皆指輪を持ってるんだろ?」
公式に魔法局で認められた魔法士は、登録情報の入った指輪を貰う。その事をは彼らに話していた。それが魔法士の証であるとも説明していた。
がずっと欲しかった指輪だ。
「そうだけど……、私は試験に落ちちゃったから……」
「だからやるって言ってるんだよ」
「?」
は岳人の言いたいことがわからず、首を傾げてその指輪を見た。クローバーが窓から入る光を浴びて輝きを増していく。
『だぁあああもうじれってぇな!』と眉間に皺を寄せて岳人は言った。
「お前もう、オレたち公認の魔法遣いだって言ってるんだよ!」
岳人たちがずっと自由時間中にどこかへ出かけていたのは、への仲直りをどうするか考えていたからである。
以前から指輪の話を聞いていた彼らは指輪が良いと考え、転々とイギリスの古い宝石店を巡っていたのだ。どの指輪がに似合うのかをいろいろと考えながら、最終的に決まったのが20件目のアンティークショップだった。そこは小さな店だったが、そのクローバーの指輪を見つけて全員が『これだ!』と叫んだのである。
四葉のクローバーは幸福の証。多くの幸福で、がずっと笑顔でいられるように、どんな試練も笑顔で乗り切れるようにとの願いを込めた。しかし、渡すきっかけが掴めず、隣の席に座る岳人へと託したのだった。
何も言わないをチラッと横目で確認してみれば、指輪を胸の前で握り締めて震えている。驚いて岳人が手を伸ばそうとしたとき、は今まで見せた笑顔の中で1番の表情を見せた。
「ありがとう……皆、ありがとう……!」
「ま、まぁな」
照れた笑みを浮かべて、岳人も満足そうに歯を見せて笑った。
こんなにも満たされた時間を過ごしたのは初めての経験で、は心から嬉しいと感じた。誰かに初めて認めてもらった。その証が今手の中にあるとすれば、これほど嬉しく幸福なことは無い。
喜びを噛み締め、日本に着いたら全員にお礼を言わなくてはとは思った。
だが、変化は起きた。
「いけませんねぇ、このようなところで大声を出されては」
「あ、あの……」
跡部財閥のフライトアテンダントの男が、そっとたちの方へ近づいてきたのである。確かに先ほどの声は大きかったと反省するが、それは周りの生徒たちも同じことだった。きゃっきゃっと楽しそうに話している生徒たちは、まだ他にも沢山いる。は戸惑い、岳人はムッとした。
「何だよ、他のヤツだって騒いでるじゃねぇか」
「ご、ごめんなさい、次からは気をつけます」
「いいえ、それでは遅いのですよ」
の言葉に考える間も無く言葉を発した男は、恐るべき物を取り出し、それをの正面に向けた。
向けられたものに、も岳人も一瞬何が起きているのか理解出来なかった。
の目の前に現れたのは、ギラッと鈍く光る拳銃。
引き金に男は指をかけ、の額に向かって銃口を向けている。
意思を持って、に向けているのだ。
あまりに突然な事で、も岳人も呼吸を忘れていた。
「もうお休みになった方が良いでしょう」
ようやくが向けられているそれが拳銃だと理解したとき、引き金が引かれて銃口が火を噴いた。
低い破裂音が響き、生徒たちが反応して悲鳴を上げた。
そして、鮮やかな赤が、シートの上に飛び散った。