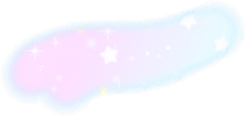
10 祖母からの手紙
魔法局の元局長であり、大魔法遣いと呼ばれていたお祖母様。そのお祖母様の家があるイギリスで暮らし始めたのは、今から2年前。
それまでは、お父さんと東京で暮らしていた。
お父さんは毎日お祖母様の仕事を手伝っていた。
お父さんには魔法の才能が無かった。
魔法を遣おうと、すごく努力したと聞いている。
お父さんの娘である私は、空を飛ぶ以外魔法は遣えなかった。
だから魔法の特訓をしていた。
お父さんに喜んでもらいたくて、お父さんの自慢できるような子になりたくて。
お父さんは魔法が遣えないことで、すごく苦しんでいたから……。
でも、私はあることに気づいた。
それは、友達と話をしているときだった。
友達は『応援してくれるから部活も頑張れるんだ』と嬉しそうに話していた。
そのときの喪失感とショックは、今まで感じたことも無いほどだった。
その言葉がどうしてここまで胸に響くのか、直ぐにはわからなかった。
でも、意味を理解したとき、ただ笑った。
だって、私は、
お父さんに、1度も『頑張れ』と言われたことが無い。
火事の事件や小学生が自殺したニュースに全く影響されること無く、氷帝学園はイギリスへの修学旅行の日を迎えた。
事件後、の態度は目に見えて明るかった。笑顔を絶やすまいとしていることが誰にもわかるくらいに。ただ笑顔で修学旅行の運営委員としての務めを果たしていった。まるで、忌まわしい事件を忘れるためのように。
飛行機の中では直ぐに寝入ってしまった。心身共に疲れ切っていたのだろうと、隣の席にいた岳人は思った。
イギリスに到着すると、生徒たちがきゃっきゃと騒ぎ始めた。コートを着ていても寒いのが伝わってくる。白い息は日本とはまだ違っているように思えて、生徒たちは楽しそうにはしゃいでいた。教師たちが生徒たちをまとめ、跡部財閥の傘下にあるホテルへと案内した。ホテルはハリウッドスターや大統領クラスの人物も利用するような立派なパレスホテルで、跡部様々といったところだ。
「流石跡部としか言いようがないな」
宍戸は天井を見上げて言った。跡部家の別荘や自宅を訪問していても、毎回のように驚いてしまう。庶民には馴染みの無い場所だった。だがこうして豪華なホテルで過ごせるのはありがたい。
ジローがふとの姿が無いことに気がついて声を上げる。
「ねぇねぇ、ちゃんがいないよ?」
「それならさっき自分の部屋に行ったで」
「…………そうなんだ」
暫くの間は自由時間だ。生徒たちにマップが配られ、ある程度の範囲内ならば自由に歩けるようになっている。連絡用の携帯を手渡されているため、何か問題が起きてもすぐに対応できるようになっている。
「部屋にこもるつもりか、アイツは」
「せっかくのイギリスなんだから、もっと騒ごうぜ!」
「お前はどこにいてもうるせぇだろうが」
跡部にそう言われて岳人はキーキー怒りながら跳んだ。
1人部屋に1人が割り当てられており、今のは本当に部屋に1人きりだ。
忍足は溜め息をついて、が走っていった方の回廊を見た。
「あの事件の事がやっぱり忘れられへんのやろ」
「そうだろうね。ついこの間の事だから……」
滝もその意見には同意した。直ぐに忘れられるような事ではない。
「つーかここだろ?」
「何がだ?」
宍戸の言葉に跡部が問い返した。
「アイツの住んでいたところって」
宍戸の言葉にハッとなる。は転入してきたときのことを思い出す。は日本出身だが、暫くの間は祖母の家で暮らしていたのだ。しかし、一緒に祖母とは暮らしていない。祖母と父親は日本で仕事をしていたのだから。
なぜが1人でイギリス生活をしなくてはならなかったのかなど、詳しい事はわからない。だが、孤独に毎日を生活していた事を考えると、強く胸が痛む話だった。
「とりあえずのところに行ってみようぜ!会って話をしなくちゃ、何も始まらないだろ?」
岳人の提案での部屋に向かう。もしかしたら、一緒にイギリスを巡るうちに気分も晴れるかもしれない。そんな事を思いながら、跡部はのいる部屋をノックした。ドア越しに『はーい』というの声がして、案外アッサリと扉は開いた。出てきたは明るく微笑んでいる。
「どうしたの?」
「いや……、何か元気そうやな」
思っていたよりも元気な様子に忍足は戸惑った。けれども、どこかおかしいと感じ取れる。
「私は元気だよ。全然平気だから。イギリスはお祖母様の故郷だし、私にとって縁が深いところだもの」
「本当にそうかな?」
「滝くん……?」
滝の言葉にが今度は戸惑った。真っ直ぐな瞳を向けられて、は言葉に詰まった。
「なんだかオレたちには、キミが無理して笑っているように見えるんだ」
「そんな、無理なんて―――」
「してるだろ」
跡部がドアに手をやりの前に出る。はうろたえるような表情で跡部を見た。
「何でもかんでも抱え込んで、無理してんじゃねぇよ」
はまた笑った。しかし、今度は普通の笑顔ではない。含みのあるような笑顔である。
「無理なんかしてないよ」
「お前、まだそんなこと―――」
「いや、もう無理なんてしないよ」
「え?」
「だって、もう何もしないって決めたんだから」
のその瞳には生気が見えない。ほの暗く、光はどこにも感じられなかった。
普段のとは全く違う態度に、全員が声を失った。いつも迷いながらも頑張っていたとは別人である。迷いも無ければ、頑張ろうとする気力も感じられないからだ。
「いったいどうしたんだよ?そんな事言うなんてお前らしく無いぜ?」
岳人がそう言い、ジローもそれに頷く。そう、彼らの知っているはこんな事を絶対に言わない。
「皆の言う、私らしいって何?いつも出来ない事を出来るようにって、バカみたいに頑張っているところ?どうせ何も出来ないくせに、信じて努力しているところ?」
は嘲笑めいた声で言う。
「世の中って不公平なことばかりだった。頑張っても頑張っても頑張っても、報われないことばかり。さほどの努力もしていない人たちだって成功しているのに、どうしてだろうってずっと思ってた。でもそれってさ、もう決まってたんだよね。出来ない人は出来ない。出来る人は出来る。努力なんて関係無しに、もう最初から決まってたんだよ」
魔法を遣える人間と魔法を遣えない人間。才能の無いものには絶対に遣えないもの。はそれを否定して必死で今まで努力をしてきた。きっと、いつか報われる日が来ると思っていたからだ。
「だから、私にはあの人たちを助けられなかった」
炎に包まれながら助けを求めていた人。
「最初から、決まっていたんだよ」
自殺した小学生。
跡部が食って掛かった。そのような話は許さないというような気迫で。
「てめぇ、本気でそんなこと言ってるのか?」
「だってそうじゃない。例えばそう、キミたちなんかが良い例よ」
「オレたちが?」
「そうよ、ジローくん。200人もの大所帯なテニス部で、どうして皆はレギュラーなの?」
「それは、オレたちが必死で練習して……」
「違うわ」
「!」
はキッパリとジローの言葉を否定した。
「キミたちは気がついていないかもしれないけれど、それは
冷たく、けれども感情のこもった声だった。
「頑張ったら報われるに決まって……!」
岳人が声を荒げた。だが、はそれを許さない。
「本当に?じゃあせめてレギュラーになれなくても、努力した人の名前をキミたちは覚えている?知っている?」
「それは……」
「言えないよね?記憶にだって残らないんだから、そんな人たちは」
は酷く悲しそうにしているにも関わらず、それでも笑っていた。
「芸能人だってそうよ。テレビの前に立っているのはほんの少し。キミたちのような人たちに踏み台にされて……だからキミたちが輝ける」
「オレたちは踏み台になんてしてへん!」
「どちらにしても、やっている事は同じことじゃない。努力した人たちは、結局スポットライトにできる影の中に消えてしまったんだから。この私みたいにね」
「お前……」
宍戸も声を失ってしまった。の言葉が、全て吐き出すように出ていく。これは全ての本気の言葉だと理解したから。
はどんな世界を見てきたのだろうか。努力しても報われない世界で、どんな光景を今まで目にしてきたのだろうか。からずるずると這い出してきた闇は、どこまでも奥底が見えない。
「私みたいなヤツの気持ちが、今までずっと認められてきたキミたちにはわかるはずがない」
「オレたちはそんな風に思ったことはあらへんで」
「その気持ちが、キミたちの当たり前になっているからでしょう?テニスの全国大会だって、皆がそれぞれに目標を持って挑んできた。練習量の違いとか、想いの強さに違いはある?無いでしょう?目指すのは同じだってわかっているでしょう?それでも、たった1校しか選ばれない。それは練習量とか想いの強さなんていうのはもう関係無いのよ。努力しなくても、努力している人の数倍上に行ける人もいる。そういうの、バカみたいでしょ?」
最初から決まっている。
「皆に死んでも思い出される人っていうのは本当に少しだけ。いくら努力したって、何にもならない。結果を残さなくちゃ忘れられて、踏み台にされて死んでいくのがオチなのよ。だから、私はもう何もしないって決めた。努力とか信じるとか、もうそんなの真っ平よ!」
「オレたちだけじゃダメなのか?」
滝が静かに問う。は目を見開いた。
「オレたちがキミを思い出すだけじゃ、ダメなのかい?」
目を見開いたままだったが、拳を固く握り締めながらガタガタと震える。思い切り首を振り、髪を振り乱して叫んだ。
「私はっ!」
「私が死ぬとき、世界が滅ばなくちゃ嫌!!」
「私を忘れる世界なんて、いらないっ!!」
そう叫ぶは、痛々しくて悲しくて、全員が声を出すのを忘れてしまった。どれくらい彼女は涙を流し、どれくらい絶望したのか、その態度と言葉で痛感した。
は目の前にいた跡部を突き飛ばして、後ろも振り向かずに走って行ってしまった。普段の跡部ならば少女1人に突き飛ばされるなどということは無い。しかし、このときばかりは油断していた。足で踏みとどまったが、の表情を見ると通り過ぎていく細腕を掴むことは出来なかった。
はホテルを飛び出した後、ある場所へ向かっていた。
イギリスの中央都市から離れた郊外。冬の灰色の空の下、は祖母の実家だった家を訪れていた。こじんまりとした、質素で決して豪華ではない家。けれど伝統のある家だ。コートを着てはこなかったが、殆ど走っていたせいで額には汗さえ滲んでいた。
白い玄関前。はデジタル式の鍵で良かったと思いつつ、番号をキーに入力していった。ほどなくして扉の鍵は解除され、は久しぶりにその金属のドアノブに触れた。中に入ると埃っぽい臭いがする玄関が見えた。
(どうしてここに来てしまったんだろう?)
理由はよくわからなかった。ただ夢中で走るうちにここへ来てしまった。ここには、自分が孤独だった日々しか残っていないというのに。
1度外へ出ようとしてはふとドアを見る。すると、郵便受けに郵便物が入っていることに気がついた。それを取り出してみると、小さな赤い花模様の手紙だった。しかも少し分厚い。は自分宛であることに驚き、そして差出人のサインを見て驚いた。
「え……?」
この字。どこかで見たことがあると思えば、それは間違いなく祖母の字だった。祖母は日本で亡くなった。その祖母が亡くなる数日前の日付が刻印された印鑑が押してあった。
は酷く同様したが、そっと手紙の封を切った。同じ小さな赤い花模様の便箋が何枚も入っていた。それも全て祖母の文字だった。愛用していた万年筆で書いたのだろうと思われる。は胸の鼓動を高鳴らせた。恐怖や喜びでもない、ただの好奇心だったのかもしれない。手紙を読み始めた。
出だしは堅苦しい挨拶で始まり、もうすぐこれから自分が死ぬことについて告げていた。は祖母の死に際を見届けることは叶わなかった。本人は病気でもう自分の身体が持たないことは知っていたらしい。
ここから先は予想もできない文章が綴られていた。
「嘘……これって……!?」
『お前の魔法と世界から魔法を消したのは、他でもない、私だ』
は目を丸くするばかりだった。そこからは一気に手紙へとのめり込んでいった。手紙にはが知りたかった事の全てが書かれていた。
『私は死ぬ間際に、私自身の中に眠る全ての力を魔法に変え、お前から魔法を奪い、世界からも魔法を奪った』
『人々の記憶も、魔法に関することならば全て消した』
なぜ祖母がこのような大それた魔法を遣ったのか、には想像も出来ない。
この手紙に書かれていることが真実だとするのなら、が考えていた【自分が魔法の無い世界に来てしまった】という説は覆される。そして、【自分は魔法を消された世界にいる】という事になる。
つまり、魔法は祖母に消されただけで、ここはの知る魔法が存在していた世界だったのだ。
「いったいどうしてこんな事を……」
これは大きな犯罪行為だ。世界を変えてしまうなど、魔法局が黙ってはいないだろう。
祖母は規律には厳しく、自分自身も1度だって違反をしたことは無い。それなのに、魔法を許可無くしかも世界を変えて人々の記憶まで消すという大罪をしてしまった。にはそこまでして魔法を遣った祖母がわからなかった。
『なぜ私がこのような魔法を遣ったのか、お前にはわからないだろう』
『この魔法は、来るべき時が訪れれば自然と解ける』
それ以上魔法が消えた理由については書かれていなかった。そして、いつがその来るべき時なのかもわからないままだった。しかし、魔法を消したのが誰だったのかはわかった。これほどの魔法を人為的に遣うことができるとも思っていなかったが、遣えるとするなら大魔法遣いであるの祖母だけだ。世界の異変を知り、そして謎も多く残る手紙に、は疲れがどっと押し寄せるのを感じた。
「お祖母様…………」
自然とはこの世にはいない人を呼んでいた。
ピリリリリリリ……ピリリリリリリ……
すると、ここでけたたましく携帯電話が鳴った。は驚いて携帯を手に取る。そしてその電話に出た。
耳に入ってきたのは、思ってもいなかった人の声だった。
このとき、自分がこれから恐ろしい事件に巻き込まれることなど、
は夢にも思っていなかった。