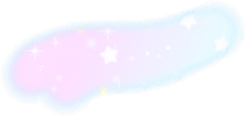
16 太陽の下で君と
日本の東京で、母の残した仕事を片付けている男がいた。かつて、魔法局を最高値にまで導いた偉大なる魔法遣いがいた。彼女は、病に倒れてからもずっとこの高層ビルで仕事を続けていた。彼は、幼少時からずっと母のスーツ姿しか見たことがなかった。気がつくと、秘書であった自分よりも先に起き、机に向って書類と葛藤している。
大魔法遣いでありながら、自分のために魔法を遣うことは無かった。18歳以上の魔法使用は、免許や許可が無ければ遣うことは出来ない。法律で禁止されている。しかし、母のような魔法局の局長などの幹部は例外とされている。しかし、母は膨大な書類を前にしても、決して魔法に頼らず自分の目で全て確認していった。そんな母の口癖は『誰と比べることもなし』であった。
男は今、母と同じようにビジネススーツに身を包んでいる。母の使っていた机で、書類に目を通していた。そこには、母が現地で困窮している人々のために遣った魔法の詳細が書かれていた。かなり大規模な魔法ばかりで、母が持つ魔法の中でも最高の技術が遣われている。母は、人のためにならば、いくらでも魔法を惜しみなく遣っていた。
「どうして……?」
向いの黒い革のソファに座る彼の妻は、俯いたままで絞り出すように言った。
「あなたは、今まであなたのお母様に見合うだけのことをしてきたじゃありませんか」
男は走らせていたペンを止めた。妻の拳になった手が震える。
「魔法が、遣えなくても……あなたはずっと、頑張ってきたじゃありませんか」
大魔法遣いの子供という立場にありながら、男は魔法を一切遣えなかった。魔法の才能が全く無かった。比べることが大嫌いだった母の背中を、いつもいつも見れずにいた。
「あなたが……あの方の本当の子供じゃないから……、だからですか?」
「…………」
母と呼んでいた女性は、本当の母じゃなかった。けれども、施設に預けられていた孤児の自分を救ってくれたのは、母と呼べるのは、あの女性だけ。
魔法の遣えない、血の繋がりの無い子供。故に、必死だった。何も持っていない自分を、彼女が見捨てていくのではないかと。もちろん、彼女がそんなことをするはずが無いことも知っていた。それでも、不安はずっと付きまとう。自分のせいで、義母の評判が落ちることが何よりも怖かった。
「本当は、魔法に関係する全ての仕事を投げ出したかったんじゃないんですか?」
魔法が嫌いだった。
いつだって投げ出せた。
何も自分に要求してこない義母が、嫌いだった。
「あの子のことだってそうですよ……。あなた、1度も頑張って魔法遣いなろうとしてるあの子を、1度も応援したことが無いでしょう?」
2人の間にできたのは、笑顔の可愛らしい少女。ほんの少し、魔法が遣えるというだけ。その中途半端さが、またもどかしくどうしようもない。
自分と同じように、娘も親の背中を見て育った。魔法が遣えずに苦しむ自分を見てきた。だからこそ、娘が頑張っていることを知っている。だが、男はそうして努力している娘を褒めようとはしなかった。1度も。
妻の問いかけに、男は静かに答えた。
「オレは今までずっと、義母さんの役に立とうともがいてきた。努力をして、ずっと努力をして義母さんがオレのことで指を指されたりしないように……」
結局は叶わなかった。
「だからわかるんだ。アイツはまだ若い。努力した先にある、絶対的に叶わないことがあることを知ったら……きっと今のアイツでは耐えきれないだろう」
どんなに頑張っても、どんなに願っても、叶わないことがある。それは世の中にたくさんある。
「まだ……そのことを教えたくない」
応援できないのではない。しないのだ。
自分が味わった苦痛を、愛しい娘にも味わせるなど、とてもできなかった。
「迷惑をかけないようにと、アイツもまた同じようにワガママを言わない子供になってしまった……」
かつての自分のように。
「それなら……」
いつの間にかドアが開いていた。声と同時に1人の少女が入って来た。ハッとなって2人は視線を少女に向ける。
大きなトランクを引きずって、入って来た少女はしばらくの間見ないうちに肩まであった髪を短く切っていた。イギリスから帰国したばかりだと見える。だが、その予定日はまだまだ先だったはずだ。ここに少女がいるはずがない。何も断りもなく行動をするような性格ではなかったはずだ。
「……」
父が、娘の名を呼ぶ。仕事場を訪れたのはもうだいぶ前のことになる。
「私の……1度きりのワガママを、聞いてくれますか?」
真剣な瞳。劣等感で反らし続けていた目が、ようやく男―――少女の父をとらえた。
父は笑う。
「1度きりなんて、寂しいこと言うなよ」
真夏の太陽が照りつける中、沢山の人々がこの会場に集まっていた。殆どが中学生である。というのも、ここが中学テニス部の全国大会があるからだ。
関東だけでも激戦区であり、その中でも強豪である中学校は注目を浴びていた。その1つである氷帝学園の彼らは、ようやく会場入りしたところだった。まだ試合前だというのに、沢山の汗を掻いてしまっている。
岳人はジャージの上着を脱ぎながら、ジローに文句を言った。
「なーんで人様にモーニングコールを頼んでおきながら、テメェは携帯の電源を入れてねぇんだよ!!」
「ぁふ……。違うC〜。電池が切れてただけじゃん」
「どっちにしても、同じことだろうがっ!!」
どうやら、ジローが起きれなかったせいで試合に登録ができなかったようだ。自宅前まで跡部がご丁寧にも車を出してくれたというのに、家から出てこなかったことも原因だ。
「そこで、まさかオレ様の車がパンクするとは思っていなかったな」
「あれは確かに想定外のことやったわ」
その後車を走らせるのは良いものの、今度は釘を踏んでタイヤがパンクしてしまったのだ。パンクした場所から、会場まで約10キロほどある。途中でバス停もあったのだが、運悪く日曜日であったために休日運行でバスは無し。結果的に、この会場まで走っていくしか方法は無かったのである。
体力があまり無い岳人にとっては、貴重な体力減に怒りを露わにする。
「ムキー!昨日はマンガ読まないで体力温存のためにすぐ寝たのに、意味がまるでねぇ!!」
「向日先輩の保護者の人、なんとかしてください。うるさいんですけど」
「オレは岳人のオカンやないんやけど」
「ダブルスのパートナーじゃないですか。同じようなもんですよ」
「今は今回のパートナーは日吉やろ」
「今回だけです、今 回 だ け」
日吉は今回だけであることを強調して言った。元々彼はダブルス向きのプレイヤーではないからだ。
怒る岳人を滝がなだめた。
「岳人、落ち着きなよ。怒ると益々体力が減るじゃないか」
「滝!お前は何で魔法遣えるくせに遣わなかったんだよ!」
ジローではなく今度は滝に食ってかかった。
200人の部員の中で、魔法を遣えるのは忍足と滝だけだった。けれど、忍足は特殊魔法行動士。いわゆる得意とする魔法能力のジャンルに偏りがあるタイプの魔法遣いなのだ。忍足が得意とする魔法は、テレポート的な魔法ではない。
そして、一方の滝は総合魔法行動士。あらゆるジャンルの魔法をバランス良く遣いこなせる、テニスのプレイスタイルで言うところのオールラウンダーだった。もちろん、全員を会場まで送り飛ばすことも可能だっただろう。しかし、滝はそれをしなかった。
「うーん……、けれど魔法は18歳未満とはいえ、免許が必要でしょ?だったら、なるべく遣わない方が良いじゃないか」
「そういうところ、滝の家は厳しそうだよね〜」
「厳しい方といえばそうかもしれないね。うちの家ではオレしか魔法は遣えないから」
「それでですか。オレの家では姉さんと母さんが遣えますよ。そんなに強い魔法は遣えないですが」
「ははは、長太郎のところは女が強いんだな」
「そういうわけじゃないと思いますが……」
「ウス」
「おお、樺地は妹が遣えるのか。オレのところは、使用人を含めて誰も魔法は遣えねぇんだよ」
(((それで良く通じるな、跡部!)))
日本では魔法を遣える人間と遣えない人間の割合はハッキリとはわかっていない。けれど、遣える人間の方が少ないことは確かだ。この会場にも、忍足や滝と同じように魔法が遣える選手はいるのだろう。
宍戸が汗ばむ帽子を被り直しながら言った。
「けど、魔法もここでは禁止だしな。遣えば反則負けになる」
「魔法は才能の1つにも関わらず、反則扱いか」
跡部が薄く笑う。彼は魔法が遣えない。だが、魔法もまた才能の内に入ると考えている。そうすれば、もっとテニスは面白くなるかもしれない。
あちこちに会場での魔法を禁止する張り紙がされていた。
「スポーツに魔法はご法度やで。遣えないヤツらとは、圧倒的に差が出る」
ここで会話が途切れた。
ここ最近、日吉・長太郎・樺地を除くメンバーには会話が途切れるところがいくつもあった。以前はこんなことは無かった。誰かが必ず何かの話題を出し、そして、それをまた誰かが笑ったり怒ったり反応を見せることの繰り返し。
会話が途切れると、メンバー全員が落ち着きの無い様子になるのだ。目を逸らしたり俯いたりイライラしたり、あるいは視線を送って口が何かを発しようとする。だが、それを毎回言い出せないのだ。
日吉が、イライラしたような口調で切り出す。
「アンタら、いい加減そういう風にするの止めてもらえますか?イライラするんですけど」
樺地も何か言いたそうにしている。恐らく日吉よりは言い方が柔らかいだろうが、同じ内容のことだろうと推測される。
「そうですよ。なんだか先輩たち最近……というかここ数ヶ月はおかしいですよ。何かあったんですか?」
長太郎も心配そうにしている。
「いや、何か、笑われるような気がして、よ」
煮え切れない言葉になる宍戸。しかし、誰も彼を責めたりはしなかった。宍戸と同じく言い出せないでいる彼らも、同じ心境だったからだ。しかし、話し出さない限りこのもやもやした気持ちは終わらない。
「まぁ、言ってみてくださいよ」
「そうっスよ宍戸さん。それに、他の先輩たちも聞きたがっていますし」
長太郎にそう言われて他のメンバーの顔を見れば、宍戸に注目が集まっていた。宍戸は仕方なさそうに視線を逸らしながら言った。
「それがな……気になることがあんだよ」
「そりゃあ、そこまでそわそわしているんですから当然でしょう」
「いちいち茶化すなよ。……なんかこう……」
そう言ったところで、宍戸の言葉が詰まる。いったいどう表現するべきか迷っている様子だった。更にイライラし出す日吉が口を開く前にジローが言った。
「雪……」
「「「!」」」
「はぁ?それはいったいどういう意味なんですか?」
日吉や長太郎に樺地は理解できない様子だったが、他の彼らはハッとしたように目を見開いた。ジローが口にした『雪』という単語に反応している。
岳人がジローの肩を強く掴んだ。そして、すがるような目をしていた。
「そう!それだよ!!」
「え……?あの、どういうことです?」
長太郎が首を傾げた。しかし、長太郎の疑問には一切触れない。忍足も跡部も上擦ったような声で言った。
「せや、雪や雪!」
「雪がこう……頭の奥の奥に降ってる感じがすんだよ」
彼らはおかしくなってしまったのだろうか。頭の奥の奥という表現も、その中で雪が降っているという表現も、全く想像できない。だが、その表現で他のメンバーには通じているようだった。あの滝でさえ頷いている。
「どう言ったら良いのかオレたちにもわからない。けれど、雪が…降っているんだ。オレたちの中で」
滝が胸の辺りにそっと手を触れる。
夢のようで夢じゃない感じ。今よりも先に起きた出来事なんて知らないはずなのに、それでもこれは未来での出来事だと思ってしまう。この先で待っていたことだと確信してしまう。
目を閉じれば降り積もるような牡丹雪が、白に埋め尽くす。何の事だかわからないというのに。
「それは去年に降った雪のことですか?」
「いや違うぜ長太郎」
「え?それを思い出しているんじゃないんですか?」
するとまた難しい顔に戻ってしまう上級生たち。
「昔あったことじゃないと思うんだよねーこれって」
「はぁああ?益々わかりませんよそれ。どういうことですか?」
論理主義である日吉には、理解しがたいことだった。普通思い出す記憶というものは、今より過去の出来事のはずだ。それ以外考えられない。
だったら、彼らの指す雪とはいったいどこで見たというのだろうか?
「あ!ここにいたんですね!!探しましたよ!!」
甲高い女性の声が聞こえてきた。そして、それは氷帝の彼らに向けられているものだった。背後に大きくて複雑な形をしたカメラを持った報道関係者の姿がある。10人ほど待ち構えていた。団体で押し寄せると、あっという間に報道陣たちが取り囲んでしまった。マイクを持った濃いメイクの女性が、跡部にインタビューを勝手に開始してしまった。フラッシュが焚かれ、さらにビデオ撮影までされてしまっている。長太郎はこの事態に怯えた様子でいる。
「な?!アンタらどっから……?!」
宍戸も驚いてフラッシュの光を遮ろうと手を振る。しかし、問答無用で報道陣たちは写真を撮り続ける。
「氷帝学園の跡部景吾くんですよね?1度は青学に負けてしまったものの、再び対戦するにあたっての心境を教えていただきたいんですけど?!」
どうやら、テニスの名門である氷帝が再び青学と対戦することが話題になっていて、それを記事やニュースにしたいと思っているようだ。氷帝は200人の部員がいて、その上に君臨するレギュラーがとてもすごい存在であることを報道関係者は知っているらしい。
滝が携帯の画面を見て慌てた。
「後10分で登録しないとオレたちは失格になるよ!」
「「「何ーー?!」」」
しかし、この状況ではどうにも前に進めない。報道関係者たちが壁のように行く手を遮っている。
「おい、テメェらどけ!!」
「逃がしませんよ!レポーターとして、絶対にインタビューに答えてもらいますからね!」
女性レポーターも全くその場を動こうとはしない。時間は迫っている。このままでは本当にテニスの試合には出場できなくなってしまうかもしれない。かといって、ここを押し通るような真似をすれば、後でどんな記事を書かれるかわからない。ニュースにも良くない場面が流されてしまうに決まっている。
絶体絶命のピンチ。命までは落とさなくても、出場権を落とされてしまう。
焦る彼らの前で、奇妙なことが起きた。
「きゃあ!?」
レポーターの持っていたマイクが、急に宙へと舞い上がったのだ。そして、次々にスタッフの持つカメラや取材道具プカプカと浮き上がっていく。高さにして3メートルほど。そのまま浮き上がった機材やマイクが、明後日の方向へ飛んで行ってしまったのだ。
「うわああ?!」
「オレのカメラが……!」
「ま、待てーー!!」
走り去る取材陣たちに残された彼らは、ポカンとしてその背中を見つめていた。
「良くわかりませんが、助かりましたね」
「ウス……」
「けど、いったい何がどうなったんだ?」
「もしかして、滝が魔法遣ったんか?」
滝が首を横に振る前に、後ろから返事が返って来た。
「私が遣ったんだよ」
振り向くと、白いノースリーブのブラウスに細身のジーンズを着た髪の短い少女が立っていた。腰には赤い色のポーチを付けている。けれど、誰も少女の知り合いはいない。
「オメェ、魔法遣いか?」
「そうだよ。最近免許取ったばかりの新米魔法遣い」
少女はニコッと微笑んだ。分類するなら少女は美しい方に入るだろう。綺麗な白い歯が口元から覗いた。
「この会場は魔法は禁止されてるぞ」
「まぁまぁ跡部くん、ここは固いこと言わないで。それに、私がいなかったらきっと大変なことになっていたんじゃない?」
「それはそうだが……」
今少女が魔法を遣って報道陣たちを追い払わなければ、試合に出場できなかったかもしれない。けれど免許を持つ魔法遣いは、国の許可が無ければ魔法を遣ってはいけないことになっている。身につけた魔法遣いの証である指輪か、使用した魔法のデータが自動的に魔法局へと送られるのだ。もし規則を破れば、それなりの罰則が待っている。新米の魔法遣いであっても、それは変わらない。
少女は『大丈夫大丈夫』と繰り返す。
「もう、許可はもらってあるの。皆の前で使って見たかったし……」
「本当かいな?魔法局に知り合いでもおるん?」
「知り合い?あー……まぁ、そんなところかな」
少し照れたように少女は微笑んだ。
「ゆっくりお礼を言っている場合じゃないですよ。そろそろ行かないと、本当に出場が危ないです」
日吉の言葉に今の状況を思い出す。
「そうだったな。そろそろ行こうぜ、侑士!」
岳人が忍足の腕を取ろうとして、『あ』と思う。そして風に髪を揺らす少女に言った。
「せっかくだから、オレらの試合見ていけよ!」
「それもそうだな」
宍戸も納得したように頷いてみせる。少女はいたずらっぽい笑みを浮かべた。
「ふふっ、最初からそのつもりでここに来たのよ」
「オレたちの試合を見にきたの?」
「うん、そうだよ滝くん」
「すっげー!もしかしてオレたちのファン!?」
ジローが興奮した様子で問う。キラキラとした太陽のような笑顔を見せた。その様子に少女もまた微笑んで答える。
「そうだね、ファンだよ。でもあの時試合は1度も見たこと無かったなって、思ったから」
サラッと答える少女に一瞬疑問が湧く。氷帝テニス部にはファンが多い。放課後の練習にはたくさんの生徒たちで埋め尽くされる。当然ファンであるならば、テニスの試合を見に来るはずだ。毎回氷帝の試合はとんでもない数のサポーターがつく。しかし、少女は1度も彼らの試合光景を見たことが無いと答えた。1度も。
しかし、それはただの偶然かもしれない。今日まで少女の時間が無くて見に来られなかっただけなのかもしれない。微かな疑問が残ったが、瞬時に消えてしまった。
それよりも気になったのは、
『あの時』というのが、
いつを示すのか。
「それじゃ応援してるから、試合頑張ってね!」
少女は、右手をひらひらと振りながら彼らに背中を向け、歩き出す。
日吉・長太郎・樺地にとっては何の変哲もない動作にしか見えなかった。しかし、その他のメンバーは少女のその後ろ姿に目を奪われてしまった。時間がこのときだけゆっくりと流れてるように凝視してしまう。
少女の右手の中指。
その指にはまっているいるのは、魔法遣いの証。
けれど、通常の指輪とは全く違っていた。
緑色のクローバーの形をしている。
幸せの印。
そして、頭の奥の奥で振り続ける雪。
その白い雪の中で笑う、
たったひとりの、魔法遣い。
「「「あああああーーー?!」」」
という絶叫に近い叫び声。
太陽の下で笑みを浮かべる少女は、
彼らが良く知るだった。
>>END
2013.08.28 ~ 2017.05.09(リメイク)