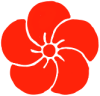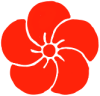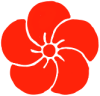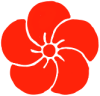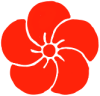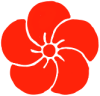第四夜 新たな予知夢
ハッとなって、は目を見開き跳び起きた。
静まり返った空間の中、耳の奥で脈打つ音が早鐘のように響く。全身が恐怖で強張り、小刻みに震えていた。冷たい汗が噴き出しており、身体は熱いのか冷たいのかわからなくなる。
一瞬ここがどこだかわからなくなるが、自分に宛がわれた光陽国の客室だと気づく。
(今のは……?夢……?)
夢にしてはやけに鮮明だった。血の濃厚な臭いも、血に濡れて光る臓物も、全てが生々しい。見ているだけにも関わらず、夢であるはずなのに、人の体温が伝わってくるようだった。
(あれは何?人が、あんな事に……!怖い!)
は膝を抱えて俯く。目を閉じることは出来なかった。汗で湿った匂いが、血の臭いになってしまいそうでただ震えるしかない。
(この感覚には覚えがある)
が十六夜だった頃、何度も視てきたあの感覚だ。
(予知夢……。でも、私はもう十六夜姫じゃない!これが、予知夢はずない……!)
が本来の姿を取り戻したときに失われた能力―――予知夢に似ているのだ。
早く朝になれば良い。薄闇の中で、はひたすら夜が明けるのを待った。
朝食の時間になり、5年生達は用意された部屋へ向かった。襖を開けると、丁度が5年生達の食事を並べているところだった。
「えっ?さん?」
「おはよう、雷蔵くん。皆もおはよう。丁度朝ご飯出来たよ」
「さん、もしかしてオレ達の朝餉を作ってくれたんですか?」
「てっきり侍女が用意してくれるのかと思っていたが、これはすごいな」
三郎は感心した様子で並べられた朝食を眺める。出汁の香りが豊かな味噌汁に、タケノコとキノコの混ぜご飯、新鮮な山菜の御浸し、魚の照り焼き、そして恐らく兵助の為に用意された寄せ豆腐だ。見ているだけでも美味しさが伝わってくる出来栄えだった。
竹谷は思わず『おほー!』と感嘆の声を漏らした。
「すげぇな!美味そう!っていうか絶対に美味いっ!」
「ふふ、ありがとう。冷めない内に食べよう?」
「「「頂きます!」」」
手を合わせて一斉にが作った朝食を食べ始めた。竹谷の予言どおり、が作った手料理はとても美味だった。一口食べるごとに旨味が口一杯に広がって、箸が止まらない。
「姫サンは料理が本当に上手だな。私はこの混ぜご飯が気に入った」
「オレは寄せ豆腐だな。毎日でも食べたいです」
「本当?いつも豆腐を食べている兵助くんに言われると、自信がついちゃうな」
ニコリと微笑むだったが、目が充血している。それに、目の下には薄っすらと隈が出来ている。気が付いた兵助が心配そうに尋ねた。
「あまり寝ていないのではありませんか?」
「えっ?」
「目が赤い。それに、目の下に隈が出来てしまっています」
「本当だ!、大丈夫か?」
「さん、何かあったんですか?」
「姫サン、もしかしてこの朝食は、目が冴えてしまったから作ったのか?」
三郎が言う事は図星だった。あのまま結局寝る事が出来なかったため、は手を動かしていた方が楽だと思ったのである。これだけの朝食を用意出来たのも、明け方から作り始めたからだ。
じっとの返事を待つ4人に、は観念した様子で苦笑いを浮かべる。
「変な夢のせいでちょっと眠れなかったんだ」
「変な夢ってどんな夢だ?」
は夢の内容を話すか躊躇った。朝食の席で、あの血生臭い夢の話をしても良いか迷うところである。
(もし、あの夢が十六夜姫の予知夢だったら……。皆に話したところで、これから起きる出来事は変えられない。でも、1人じゃなくて皆と一緒なら、悪い出来事を変えられるかもしれない!)
これまでのは、視てしまった予知夢を誰にも話さなかった。他の人を巻き込んでしまう事を恐れ、自分で何とかしようとした。もし他の人を頼っていたら、何かが変わっていたかもしれない。
(本当に予知夢だとはまだ決まっていない。私の勘違いかもしれないし)
は重い口を開いた。
「すごく嫌な感じの夢だった。村みたいなところに私がいて、多分……村人だと思う人達が……沢山亡くなっているの。身体が皆バラバラになっていて、ち、血まみれ……で……。とても……人間が出来るような殺し方じゃなかった……」
「ひえっ!?バラバラだって?!」
「それは、酷い……」
竹谷も雷蔵も顔が青くなる。
「考えただけで気持ちが悪くなりそうだ。姫サンが眠れなくなるのも仕方がない」
「バラバラで、人が出来ないような殺し方……。それって、どこかで……」
雷蔵がそうつぶやくと、兵助がぽつりと神妙な面持ちで呟いた。
「初代鬼姫」
「あっ!言われてみれば、彦兵衛のじいさんも、『鬼姫が城の人間達を引き千切って殺した』とかって言ってたよな」
「そういえばそうだよね!もしかすると、そんな話を聞いてしまったから、さんが夢に見てしまったとか……?」
伝説となった初代鬼姫―――朔。素手で城内の人間を引き千切るというおぞましい殺し方は、まさに鬼の所業だ。そんな話を聞いたから、もそのようなおぞましい夢を見た可能性がある。
ここで兵助は更に恐ろしい可能性についてに問いかけた。
「さんは、この夢をただの夢ではなく、十六夜姫の予知夢だと考えているのではありませんか?」
「「ええっ!?」」
竹谷と雷蔵は予想もしなかった兵助の言葉に、思わず驚きの声を上げてしまった。三郎は良そうないの発言だったようだが、表情は明るくない。
「まぁ、姫サンは悪戯に私達を怖がらせるような事はしないだろう。こういう話をするのは、重大な意味がある。そうだろう?姫サン」
は眉間に皺を作って頷いた。
「私はもう十六夜姫じゃない。でも、何だか……予知夢を視たときのような感覚がしたんだ。違っていたら本当に有難いんだけれど、もしかしたら、本当にどこかの村の人達が夢のとおりに殺されてしまうかもしれない。そう思ったら、皆に協力してもらいたくて……」
本当に予知夢だったとしても、そうではなかったとしても、どの道5年生達に迷惑を掛けるだろう。そう思うと語尾は段々小さくなっていった。
「ごめんね。皆に迷惑掛けちゃうよね……」
「謝る必要はありませんよ。僕は、さんが困っているときに何も出来ない方がずーっと嫌ですから」
「そうだぜ、オレ達に遠慮する事ねぇし。要するに、それらしい村に行って、何も起きない事を確かめれば良いんだ」
「何か異変が起きたとしても、その前に食い止めましょう。オレ達の事を頼ってください」
「姫サンの事は私達が全力で護る。約束しよう。だから姫サンは笑っていてくれ」
頼もしく、そして優しい言葉が降り積もる。はようやく作り笑顔ではない明るい表情を取り戻した。
「皆、ありがとう!皆に話して本当に良かった」
の硬い雰囲気が柔らかくなり、5年生達も安堵する。
「朝食後にさっそく調べてみるか。、夢に出てきたっていう村に見覚えはあるか?」
「ううん、わからない。でも、これが本当に予知夢と関係あるなら、予知夢は私の身近で起きるはず。だから、光陽国に近い村で起きると思う」
「なるほど。それなら、彦兵衛さんに1番ここから近い村について聞いてみましょう」
雷蔵の提案で、達は彦兵衛に城下町から近い村の地図を書いてもらった。もちろん、予知夢の話を彦兵衛にはしていない。村まで遊びに出かけると伝えてある。そして、達はさっそく村へ出かけることにした。
城下町から半刻ほど歩いたところで村が見えてきた。村の名前は稲葉村。どこにでもあるのどかな村だ。
「何か普通の村だな。特に騒ぎは起きていねぇし」
「そうだね。村の人達の様子はおかしくないよ。ただ、僕達みたいな余所者には少し警戒しているみたいだね」
村人はあからさまな敵意は無いものの、多少達が気になっている様子だ。チラチラと視線を感じる。
「村は閉鎖的な雰囲気があるよな。城下町からの出入りはあるみたいだが」
三郎が指さすのは、城下町の帰りと思われる村人達だ。荷車には城下町で売られていた品が乗せられている。
「ここからだと城が小さく見えるね。それから、あっちはこの前雨宿りをした廃城だね。廃城の方が近いみたい」
は青空の下に佇む光陽国の城と、それよりも大きく見える廃城を指さした。どうやらここはまだ光陽国と月陰国が1つだった頃の城下町らしい。ここへ来る途中、それらしい痕跡を見かけている。
とりあえず、村の様子がおかしくない事には安堵した。しかし、兵助は釘を刺す。
「まだ何も起きていないだけで、これから起きる可能性もあります」
「ちょっと、兵助……」
「ううん、兵助くんの言うとおりだよ。この村でこれから何か起きるのかもしれない。この村を少し見て周ろうよ」
「わかった!」
「わかりました」
「そうですね。僕もそれが良いと思います」
「それなら手分けしよう。半刻後、そこの茶屋に集合しよう」
「うん!」
達は村の中を見て歩く事にした。
それぞれが村で変わった事が起きていないか、怪しい人物を見ていないか、村人に尋ね歩いた。しかし、村は穏やかそのもので、が夢に見た凄惨な現場はどこにも見当たらない。それらしい証言も得られなかった。村人達は『知らない』『見ていない』『わからない』の繰り返しである。
有力な情報を得られないまま、は集合場所の茶屋へ戻る時間になってしまった。以外の全員は既に茶屋に集まっている。は小走りで茶屋へ入った。
「ごめんね、待たせちゃって。皆、村の様子はどうだった?」
「私は特にこれと言って怪しい者は見なかったよ」
「僕もです。村の人達も怪しい人を見ていないと言っていました。村の外から来ているのは僕達くらいでしょうか」
「おばちゃん達の集まっている井戸端会議にも顔を出してみたけれど、やれどこの旦那さんがだらしないだの、子供が悪戯をして困っているだの……。永遠に終わりそうにない世間話ばかりだったぜ」
竹谷は散々近所の奥様方に絡まれたのか、少々疲れた表情だった。
「とにかく、おかしな出来事も起きていないみたいだったな。の方は?」
「私も皆と同じだよ。村の人達は最近の出来事を聞いても、農作業の事とか、ご近所付き合いの事とか、特に変な事は無かったみたい。村の人達が特別暗かったり元気が無いわけじゃないみたいだし。あ、光陽国と月陰国が、和議を結ぶ準備がある事は知っているみたいだったよ。戦を回避出来て安心したって言っている人もいた」
戦が始まれば、村も大変な騒ぎになる。月陰国との険悪な雰囲気を感じ、気持ちが落ち着かない日々を過ごしていただろう。現在は和議を結ぶ準備がある事が村にも伝わり、安堵している村人は多かった。
「この村は城下町に近い。だから外からも商売人がやって来る。村人によると、完全に閉鎖的な環境では無いらしいが、ここ数年は外部からの出入りは禁止されていたそうだ。城下町の人間以外は稲葉村を出入り出来ないように、光陽国が制限していたらしいぞ」
三郎の言葉に兵助が付け加える。
「ああ、それだったらオレも聞いた。月陰国との関係がここ数年悪化していたせいで、国内の情報が漏れないようにするためだとか。まだ正式に月陰国と和議を結んでいないから、一応今も出入り制限はされているらしい」
確かにここ数年は月陰国と関係が悪くなっており、戦がいつ起きてもおかしくない状態だった。そのため、間者の出入りを防ぐために国境付近に関所を設けているのだ。現在は達の活躍もあり、和議が結ばれる準備をしている。しかし、和議が正式に結ばれるまでは、念のために光陽国や稲葉村のような周辺の出入りを制限していた。
「それってつまり、村人以外の人間が来れば直ぐにわかるって事だよね?」
「確かに、城下町から商売に来る人達も毎回同じ顔触れだろうから、村人なら直ぐに気づくはず……」
「だな。この村もそんなに大きくねぇから、噂になれば直ぐに知れ渡る。……えっ?もしかすると、の夢で村人達を殺していたのは、同じ村人か?!」
「ええっ?!ま、まさか……。いや、でもやっぱり……!?だけど、1番可能性が……。うーん、あ、アレかな?それとも、コレかな!?」
「ちょっと待って!そもそもまだ村では何も起きていないから、落ち着いて―――」
「全員、落ち着いて聞いて欲しい」
これまで黙っていた兵助が、やけに真剣な表情でと発言する。まるでこの世の重大事項を告げるかのように。ゴクリと唾を飲み込む音がどこからともなく聞こえてくる。
「まず、何か食べよう。さっきから店のおばちゃんが、オレ達を視線で殺すように睨んでいる」
「「「?!」」」
兵助の視線の先を追ってガバッと後ろを振り向けば、仁王立ちになった店のおばちゃんが立っている。話すだけ話をして、全く注文をしない達に憤っているのだ。この時間帯は特に昼食の時間帯で、戦場さながらの忙しさだ。おばちゃんの背中に燃え盛る炎が見えた気がした。
三郎は壁に貼ってあるメニューを指さして叫ぶように注文をした。
「お、おばちゃん!私は狐うどんを頼む!」
「じゃあ、私は焼き魚定食をお願いします!」
「オレも同じやつ!」
「僕は狸蕎麦!」
「オレは田楽定食を頼む!」
「はいよっ!毎度あり!」
般若の顔をしたおばちゃんが一転、菩薩のような微笑みを浮かべて厨房の奥へと消えていった。達は命を繋ぎ止める事が出来て安堵した。
「……とりあえず、飯にしようぜ。話はそれからでも遅くない」
「そ、そうだね。お店の人に迷惑をかけちゃうし」
やがて暫く待っていると、おばちゃんが次々に注文した料理を運んで来た。湯気に乗った温かな香りに包まれ、切羽詰まっていた心が一気に解れる。はホッと息を吐いて、味噌汁に口をつける。ほっとした気持ちになれる優しい味が口いっぱいに広がった。他の皆も満足そうな顔でそれぞれの料理を口にしている。
おばちゃんがに達に興味津々で声を掛けてきた。
「アンタ達、この辺じゃ見かけない顔だね。見たところ城下の行商人じゃなさそうだけど」
「あ、はい……。えっと、私達は……」
行商人ではないが、かと言って城で生活をしている事などは話し難い。は鬼姫の事を思い出した。ここから見える廃城は、初代鬼姫がいた場所だ。物珍しさに城下町からやって来る者もいるだろう。
「私達、この辺で伝わっている初代鬼姫の祟りについて知りたいなと思って、城下町から来ました」
がそう言った瞬間、水を打ったように店内が静まり返った。そして、ざわざわと落ち着きが無い声が店内に広がっていく。おばちゃんも怯えや恐怖、不安の混じった表情に変わった。
「あ、あの……?」
「どっ、どうしたんだよ……?」
竹谷もと同じように、村人達の様子がおかしい事に戸惑った。
「僕達何かおかしい事を言いましたか?」
「アンタ達も、初代鬼姫様の祟りを知りたいってクチかい?教えてやっても良いけど、あの廃城へは近づかない方が良い。今でも鬼姫様があの辺をうろついているって話だからね」
「えっ?そんな事……」
は冗談だろうと思った。しかし、からかいなどではなく、おばちゃんはあくまでも真剣だ。
何かがある。全員がそう確信した。
兵助が三郎の視線で合図を送ると、三郎が口を開いた。
「なぁおばちゃん、私達にその初代鬼姫の事を教えてくれないか?私達は知りたい事がわかれば、城下町へさっさと帰る。悪戯に村を混乱させるつもりは無い」
「わかったよ。話してやるから、廃城には近づかないでおくれよ。あたし達はただ穏やかに暮らしたいんだからさ」
おばちゃんは、達を厨房の更に奥にある居住スペースへ案内してくれた。
「アンタ達、どこまで鬼姫様の祟りについて知っているんだい?」
「初代の鬼姫と呼ばれた朔姫が、あの廃城で城の者達を次々に引き千切って殺したっていう事です」
は、赤眼病の事や赤眼病の実験については伏せた。恐らくこの事実は光陽国の城の者でも、一部しか知らないだろう。
おばちゃんは心底嫌そうに首を振って『やれやれ……』と呟いた。
「噂を面白がって、廃城へ肝試しに行く連中が多くて困るよ」
「オレ達はそんなつもりじゃ―――」
「八左ヱ門」
「しーっ!」
兵助と雷蔵に竹谷が制される。確かに肝試しのような遊び目的で出かけるつもりではない。しかし、おばちゃんに本当の目的を説明をするのも難しい。ここはおばちゃんのペースに合わせておく方が得策だ。
「この村は城からも近いからね。鬼姫様の伝説は、ここらの子供だって皆知っている。アンタ達だって、鬼姫様が城の者達を殺し回った事を知って、面白半分で廃城へ肝試しに行くつもりなんだろう?」
これは彦兵衛から聞いている話と同じだ。知っている話とは言え、ドキリと心臓が跳ねる。
ところが、おばちゃんはここから彦兵衛からも聞かされていない話を始めた。
「鬼姫様は、ただ城の者達を皆殺しにしたからそう呼ばれているんじゃないよ。鬼姫様は、祟りを起こす前にこの村に埋葬されているんだ」
「えっ?!埋葬!?」
「埋葬された……?それだと、つまり鬼姫は亡くなった後に蘇ったということですか?」
兵助の問いかけにおばちゃんは神妙な顔で頷く。
「噂では、鬼姫様は城の者に殺されたっていう話さ。それを怨みに怨んで墓から蘇り、城の者達へ復讐したんだよ。全く本当に恐ろしい話だよ。ここらじゃ大人だって鬼姫様の事は恐れていて、誰も廃城には近づこうとしない」
おばちゃんは鬼姫の祟りについてブツブツと呟いている。
は、こそっとおばちゃんには聞こえないように5年生達に話し掛けた。
「いったいどういう事だと思う?赤眼病の患者は、亡くなると砂になってしまうはずだよね?」
「そうですよね。僕達だって、その現場を見ています。初代の鬼姫が、亡くなった後に蘇れるはずは……」
「砂になった身体が再生するとも思えない。語り継がれてきたせいで、おかしな伝わり方になってしまったのか?」
「いや、鬼化する前の段階で死亡したなら、砂にならないだろう」
「けどな兵助、彦兵衛のじいさんは鬼姫は拷問で鬼化したって言ってただろ?」
もしおばちゃんの語る鬼姫の祟りが本当ならば、やはり何かがおかしい。赤眼病の患者は人知を超えた力を手に入れる。だからと言って、砂になった人間が蘇るなどという気味が悪い話、果たして本当にあり得るのだろうか?
疑問が浮かんでくるばかりだったが、その疑問の中からはある可能性に辿り着いた。
「……もしかして、私が十六夜姫だったみたいに、別人が鬼姫の身体に入っていたとか?」
「みたいに?」
「確かに、姫サンのような例がある。私達がそれを目撃している。だが、そんな事がそう何度もあるものか……?」
は十六夜の身体に入り込み、十六夜として過ごしてきた。十六夜の心臓を貫かれて絶命した後は、砂になって身体が消滅した。しかし、その後は本来の姿を取り戻す事が出来た。同じ事が朔にも起きていたのかもしれない。しかし、それを確かめる術が達には無い。
疑問はそれだけではない。はハッとしておばちゃんに質問をした。
「おばちゃん、伝説の鬼姫は蘇った後に城の人達を殺したんですよね?」
「そう聞いているよ」
はおばちゃんの答えに対し、強烈な違和感を感じた。
「村で埋葬されたんだったら、村で蘇ったはずですよね?村人は鬼姫に殺されなかったんですか?」
「「「?!」」」
のこの質問に対して、5年生達もようやくの言わんとしている事に気が付いた。
鬼化した者は、正気を失う。城の者達を皆殺しにするほどの精神状態だ。見境なく人を殺してしまってもおかしくない。村の墓から蘇ったと伝えられているのであれば、城の者よりも村人を真っ先に殺しているはずだろう。
おばちゃんも不思議そうに答えた。
「そうさね、確かによくよく考えてみればおかしな話だ。けど、村人が殺されたという話は伝わっていないよ。鬼姫様が殺したのは、城の者達だとしかわからないね」
「そうですか……」
「本当に村人は殺されたっていう話は無いんですよね?」
念を押して雷蔵が尋ねれば、面倒だとばかりにおばちゃんは顔を顰めた。
「そうだよ。どういうわけか、鬼姫様は村人を殺していない。それもまた面妖な話だけれどね。だから鬼姫様は恐れられているのさ。それよりアンタ達、さっさと食べて、払うもん払って帰っておくれ。後がつかえてるんだよ」
「あっ、ごめんなさい!」
「話しかけてきたのおばちゃんじゃん……」
竹谷はぼそっと呟くが、おばちゃんの耳には届いていない様子だった。どうやら都合の悪い事は耳に入らないらしい。
全員が注文をした料理を急いで食べ始める。美味しいはずの料理の味が、なぜだか濁っている。胸の内はもやもやとするばかりで、ちっとも晴れなかった。
料理を食べ終わった後、早々に代金を支払って店を出た。
「姫サンの夢が予知夢なのかどうかはわからなかったが、初代鬼姫の話を聞けたのは良かったんじゃないか」
「そうだよね。わからない事が増えた気もするけれど、初代鬼姫の事を知れて村に来た甲斐があるよ」
「彦兵衛のじいさんの言っていた事と、村に伝わっている鬼姫の祟り……。ものすごく食い違っているわけじゃねぇけど、どこかおかしい感じがするよな」
「ずっと昔の話だ。人伝で内容が変化していく事は良くある」
「鬼姫の事はひとまず置いておいて、僕達はもう少し村の様子を見てから帰りませんか?午後になって城下へ行っていた村人も帰ってくるかもしれないですから」
「うん、そうだね。もう少しこの村を調べてみよう。予知夢の兆候があるなら、私はそれを止めたい……」
しかし、結局恐ろしい予知夢と繋がるような情報は得られなかった。村は平穏そのものであり、怪しい人物の出入りも無い。村でこれから何かが起きるなど、誰も想像出来ないだろう。
は平穏そのものの村の様子を見て、安堵の表情を浮かべる。
「鬼姫の祟りの事は気になるけれど、私の怖い夢が予知夢だっていう感じは無いよね」
「だよな!村は平和っていう雰囲気だしよ」
「今のところそんな感じは全くしませんね。今日はもう遅いですし、帰りましょう。城で彦兵衛殿が待っています」
「そうだね。あまり遅くなると、日が暮れてしまうし」
の恐ろしい夢は、予知夢ではない。村はの視た夢の出来事が起きるとはとても思えなかった。予知夢に繋がるような事も起きなかった。達は安堵をして、城下町へ続いている一本道を戻る事にした。
帰り道、見上げた夕暮れは血のように赤く染まっていた。
次の日、稲葉村は壊滅状態で発見される。
村にいた全員が、何者かに引き千切られたかのような肉塊になり、鮮血で地面は赤く染まる。
まるで、今日見上げたこの夕暮れのように。