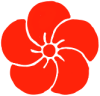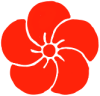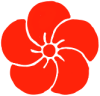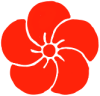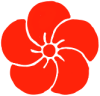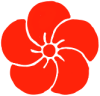第三夜 初代鬼姫の祟り
落ちた!!
は衝撃に備えて身体を硬くし、ぎゅっと目を瞑る。どのくらいの高さがあるのかわからないが、尻餅をつくだけでは済まされないと思った。
ところが、の耳に飛び込んできたのは衝撃音ではなかった。
「大丈夫か?!」
「八左ヱ門くん……!」
心配そうな竹谷の声だ。の腰には竹谷の左腕が回されており、力強く抱えられている。竹谷の右腕が鍵縄を投げ、どうにかぶら下がっている。助かったのだ。
「ハチー!さーん!」
「大丈夫かー?!」
雷蔵と三郎がの落ちた穴を覗き込んでいる。竹谷もも上を向いて無事を伝えた。
「どうにか大丈夫だ!」
「私も大丈夫!八左ヱ門くんが助けてくれたから!」
「そうですか、良かった〜!」
「待ってろ!今引き上げ―――」
「待て三郎。このまま引き上げようとすれば、また床が抜けるかもしれない」
久々知の言うとおりで、2人分の体重を引き上げるのは難しい。今度こそ竹谷もも落下してしまうかもしれない。でも、このままでは2人共ぶら下がったままだ。
「ねえ!そこからちょっと照らしてみてくれないかな?このまま下に降りた方が安全かもしれない」
「確かにそうだな。兵助、火を持ってきてくれ!」
「わかった」
兵助は砕けた床板を束ね、囲炉裏の火をそれに移す。そして穴の中を照らすようにかざした。
と竹谷はその灯りをを頼りに自分達の下を確認した。少し薄暗いが、床は見えている。竹谷の身体能力なら、を抱えて着地出来そうだ。
「ハチー!行けそう?」
「ああ!これくらいなら平気だ!、しっかり掴まっていろよっ」
「うん!」
竹谷は鍵縄から右手を離し、を抱きかかえながら飛んだ。は竹谷に掴まって衝撃に備えた。
ドンという衝撃が伝わり、2人は無事に着地することが出来た。それを見届けた上の3人も、ほっと胸を撫で下ろした。
「姫サン!私達もそっちへ行く!」
「えっ?でも、私達がそっちへ行く方が……」
どちらにしてもこの廃城から帰るためには地上へ出なければならない。達が三郎達のところへ戻る方が良いと思われた。しかし、久々知や雷蔵は首を横に振る。
「さんが落ちたところは恐らく侵入者を落とすための罠でしょう。そうでなければ、地下にこんな空間があるがずありません。下手に動くと危険です」
「僕達が安全にそっちへ降りる方法を探して合流します。今はそこでじっとしていてください。ハチ、さんの事頼んだよ!」
「任せとけ!」
「ハチ、2人きりだからってやらしい事するなよ〜」
「ばっ?!しねぇよアホ!!」
ニヤニヤした三郎にからかわれ、竹谷がカッと顔を赤くする。三郎は手をヒラヒラと振って、雷蔵と久々知と一緒に地下へ通じる道を探しに行った。はただ困ったように笑うしかない。竹谷は三郎に対して怒りながらも変な汗を掻いている。
「ったく三郎のヤツ……!ごめんな、三郎が変なこと言って……」
「私は気にしてないよ」
(あーオレ今絶対に顔赤いんだろうな。暗くて良かった……)
もし明るい場所だったら、竹谷は今度こそどう振る舞ったら良いのか悩むのだろう。
竹谷が片手で顔を覆っていると、反対側の腕にの手が触れてきた。しかもそれは撫でるようにゆっくり動いている。
「ひぇっ!?!?」
三郎の言葉が現実味を帯び、竹谷の心臓がバクンと大きく跳ね上がった。
はぎゅっと竹谷の腕を掴み、安心したように呟いた。
「良かった。八左ヱ門くんに怪我が無いみたいで……」
「!」
は竹谷の身体に触れて怪我をしていないか確認をしたのだ。
沈黙が訪れ、雨のメロディーがと竹谷を包む。
「八左ヱ門くん……?」
急に竹谷が黙り、は不思議そうに首を傾げた。竹谷の様子を確かめたくても、この暗さでは良くわからない。
「あの、どうし―――」
「ごめんな、」
それは先ほどのような慌てた声ではなく、雨の音のように優しく語り掛けるような声だ。
竹谷に触れているの手に、一回り大きな手が重なる。
「さっきオレ、がいつか元の世界に帰らなくちゃいけないって聞いて、我が儘言った。は来たくてここに来たわけじゃねぇもんな」
「八左ヱ門くん……」
「は酷い事言ったオレを、こうして怪我をしていないか心配してくれた。だから、ごめんな」
「……私こそ、いきなりあんな事を言ってごめんね。今の私には、いつ帰るとか、そもそも帰れるかさえもわからないけれど……。でも、ハッキリ言える事が1つあるよ」
は目を細めて柔和に微笑む。
「皆との思い出、皆の事、絶対に忘れないから」
のこの一言で、竹谷は暗雲が晴れていくのを感じた。
竹谷はと離れる事が単に嫌だったわけではない。それに気づいてはいなかったが。
元の世界にが帰ったとき、自分達を忘れられる事が何よりも嫌で、とても怖かったのだ。
また竹谷に嫌な思いをさせてしまったのかとは焦る。しかし、竹谷は満足そうに言った。
「、ありがとう!その言葉でオレ、オレ達は皆きっと大丈夫だ。オレ達も、の事を絶対に忘れねぇから」
「……うんっ!」
も同じように思っていた。
このままもし元の世界へ戻ってしまったら、そのとき彼らは自分を忘れてしまうのか?
忘れたいと思われてしまうのか?
それは仕方なない事だと思いつつ、心のどこかで忘れて欲しくないという欲があった。その欲を隠して、消さなければいけないと思っていたのに。
どうやらその欲は、消さなくても良いらしい。
にっこりとお互いに微笑み合っていると、バタバタ走る複数の足音が聞こえてきた。三郎と雷蔵、そして久々知だ。手には小さな松明が握られていて、辺りがようやく橙色の光で照らされた。
3人はよほど急いで来たのか、疲れた様子が窺える。
「さん、ハチ、大丈夫?!」
「ここまで降りるための隠し通路があった。そこから上に戻れるぞ」
「そっか、良かった」
「八左ヱ門、何だかスッキリしてした顔をしているな」
「えっ?ああ、まぁそんなところだ」
竹谷がをチラッと見ると、も笑顔で応えた。竹谷との間に流れる空気が穏やかになった事に気づき、3人はホッとする。
「そういえば、ここへ来る途中、兵助は文持ってなかった?」
雷蔵に話しかけられ、久々知は懐から茶色く汚れている文を取り出した。
「何だそれ?」
「さっき女の子に声を掛けられて、コレを渡された」
「なるほど〜、女の子からの恋文か〜。ったく、モテるやつはこれだから―――って、こんな廃城に女の子がいるわけねぇだろ!?」
「でも、確かに女の子だったぞ」
「おい、それ絶対に幽霊とかお化けなんじゃねーの!?」
「そんな非科学的なものが存在するわけないのだ」
「もしかして、兵助くんって視える人……?」
三郎と雷蔵にが尋ねると、2人は困ったような顔になった。
「どうやらかなりハッキリ視えるらしい。人間と幽霊の区別がつかないくらいに」
「兵助本人は、幽霊の類を全然信じていないんですけれどね……」
「それはすごいね……」
霊がハッキリ視えるせいか、久々知は生身の人間だと思っているらしい。
「絶対呪いの文だぞソレ!!絶対に読むなよ!!」
「はぁ……?」
「あっ!?だけど、そのまま捨てるのも呪われるんじゃ……?!」
「まったく……、それじゃどうすれば良いんだよ?」
「とっ、とりあえず持っておけ!」
下手に幽霊が視えない竹谷からすれば、幽霊からの文はめちゃくちゃ恐ろしいようだ。久々知は興味無さそうに文を懐へ仕舞った。
「あれ?奥に何かあるよ?」
「本当だ。今まで灯りが無かったから気づかなったな……」
が指さす方には、ボロボロに錆びている鉄の扉があった。しかし、それでも頑丈なようで、同じ鉄の古びた錠前がついている。扉の下の隙間から黒ずみが広がっていて、思わずは足を退けた。背筋が冷たくなったのは、ここが地下だからという理由だけではないだろう。
「何だこの扉……。地下にあるのは普通牢屋や倉庫のはずだよね?」
雷蔵が変に思うのも無理はない。牢屋ならば、扉ではなく鉄格子にして閉じ込めておかなければならない。閉じ込めた者が逃げ出さないように見張るためだ。しかし、この扉には小窓さえ無い。
倉庫にしてはこの扉は厳重過ぎる。
「おほー!もっ、もしかしてお宝かっ?!」
「いや、それは無いだろう」
一瞬にして目を輝かせた竹谷だが、久々知の一言で一刀両断される。
「何でだよ兵助?!こんなに頑丈な扉なら、お宝を隠していてもおかしくねぇだろ?」
「私もそれは無いと思うぞ」
「三郎までそんな事言うのかよ〜」
「よ〜く考えてみろ。仮にこの先にあるものがお宝だとしたら、お前も姫サンも死んでいるはずだ」
「「え?!」」
予想もしなかった言葉にと竹谷はぎょっとした顔になる。まさか自分が死の危機に瀕していたなど、全く考えていなかったのだから当然である。
久々知は2人のために淡々と説明をした。
「宝が隠されているのが地下なら、侵入者をわざわざ地下へ無事に落とすような罠を仕掛けますか?地下に落とすなんて、宝を盗んでくださいと言っているようなものです。落とすなら、その真下に針山でも用意して、確実に侵入者を仕留める落とし穴にするでしょう。でも、今のさんと八左ヱ門は無事で針山も無い」
「それじゃ……、まるでさっきの穴は、この扉の向こうに侵入者を案内するためみたい」
「つまり!本当の罠はこの扉の向こうにあるって事か?!」
「お宝ではない事は僕にも納得出来るけれど、罠だったらこんなに鍵を掛けておくかな?これだと罠にかけたくても侵入者は中に入れないんじゃ……?うーん?」
「鍵を大げさにする事で、益々中に宝があると思わせる……という考えかもしれない」
「「「う〜〜〜ん……?」」」
久々知の一言で、余計に扉の向こうに何があるのか予想不可能となった。
「この時点でもわかる事があるよね?」
は眉を寄せて全員に呼びかければ、こくりと頷きが返ってくる。
「「「絶対に良くない事がこの先にある!」」」
「その根拠は?」
「「「忍者の勘!」」」
「……私にも忍者の勘があるのかもしれない」
にも、この扉の向こうには何か良くないものがあるとしか思えなかった。
それは根拠の無い当てずっぽうではあるが、5年生達も同意見のようだ。
しかし、このまま立ち去ってしまえば、『あれはいったい何だったのか?』という疑問が付きまとってくるだろう。それはそれで困る。
はふうっと息を吐いてから覚悟を決めたように言った。
「やっぱり、扉を開けてみようよ。本当は開けない方が良いかもしれないけれど、他にここに迷い込んだ人が開けてしまって、危険な目に遭っちゃうかもしれないし。それに……、私は知りたい」
が言うまでもなかったようで、の意見に全員が賛成した。
「私も気になる」
「僕もだよ」
「の事はオレ達が護るから、心配すんな」
「では、開けるぞ。さんはオレ達の後ろにいてください」
「うん、わかった。気を付けてね」
は竹谷の後ろに隠れるように下がり、久々知は掛けられた錠前に手を伸ばした。
良く見れば、錠前は錆びついているものの、誰かが抉じ開けようとした形跡は無い。どうやら鍵が掛けられてからは、達以外に発見されていないようだ。
久々知が錠前を少し調べてから苦無を取り出し、脆くなっている部分を強く突いた。火花が散り、何度もやっている内にヒビが入る。ついに錠前は真っ二つに割れた。ガシャッと無機質な音を立てて落ちる。
「これで良いな。雷蔵、三郎、扉を開けてくれ」
「わかった!」
「はいよ!」
2人は鉄の重厚な扉の取っ手を持ち、力を思い切り込めて引っ張り開ける。ギギギ……という錆びた音が響いた。
はその先に待つ光景を目に焼き付けようと見開く。
そして、扉は完全に開ききった。
「こ、これって……!」
は口元に手を当てて驚嘆した。指先から血の気が引いていき、顔はみるみる青くなった。と一緒にいた彼らも顔を歪めて引き攣らせた。
扉の向こう、その先にあったのは黄金の宝の山でもなく、侵入者を嵌めるための罠でもない。
事切れて枯れ枝のようになった複数の遺体が、窪んだ暗い目で訴えてくる。
ここは、拷問部屋だ、と。
廃城から達が戻ったときには、もう夜になっていた。
雨が降っていたこともあり、彦兵衛はを心から心配していた。と遊びに出かけていた5年生達を見るなり目くじらを立ててしまいそうになるが、や5年生達の表情が酷く暗い。意気消沈としている様子を見て、彦兵衛は疑問符を浮かべてしまう。
だが、達から廃城での事情を聞いて直ぐに彦兵衛も神妙な顔つきになり、押し黙ってしまった。それから重い口を開き、『まずは冷えた体を温めてください』とだけ告げた。
達は濡れた身体を風呂で温め、食事を取った。全員箸を動かす手が鈍かったが、彦兵衛の厚意と心配をかけてしまった分、口に運べるだけ食事を腹に入れた。
食事後、予想どおり彦兵衛がやって来て人払いをする。
「聞きたいことはわかっています。あまり良い話ではございませぬが、それでもお聞きになりたいですかな?」
「はい。見てしまいましたから、何も知らないままでいることは出来ません」
しっかりとした声でが答えると、5年生達もそれに頷く。そして、彦兵衛の話に耳を傾けた。
「あの廃城は、まだ光陽国と月陰国が1つだった頃の小さな国だった時代に建てられた城です」
「確か、元は薬師の里だったんですよね?」
「はい、様のおっしゃるとおりです」
は彦兵衛から十六夜姫として生活していた頃にその話を聞いていた。そして、5年生達にもある程度その辺の知識はある。
光陽国と月陰国は元々は薬師の里で、そこから国へ発展したのだ。里の薬師の腕前は評判が良く、質素だが順風満帆な生活が送れるところだった。
ところが、里の周りで戦が頻発するようになり、薬師の里も戦に利用出来る薬の開発を行うようになっていった。そして、赤眼病と出会い、それが遺伝の病気だとわかると悍ましい人体実験を繰り返し、戦に使える人間兵器を生み出そうとしたのである。
「あの当時は表沙汰にはされていなかったものの、赤眼病の研究と開発を行っていました。恐らく、様達が見た拷問部屋は、その当時に使われていた研究施設の一部なのでしょう。あの部屋は正確に言うと拷問部屋ではなく、実験室だったと聞き及んでいます」
「実験室……?あの部屋が?」
雷蔵が拷問部屋を思い出し、苦い顔になる。実験とは程遠い部屋に寒気が走る。
三郎も同じく不快感を隠そうともせず舌打ちをした。
「赤眼病は鬼化状態になると化け物みたいな力を発揮する体になる。だから、その化け物の力がどのくらいあるのかを実験で調べたかったんだろうよ。どのくらい拷問に耐えられるのか?とかな」
三郎の隣に座る久々知はあくまでも表情には出さない。しかし、膝に乗せられている拳を硬く握り締めていた。
「確かにその可能性は高い。元々は戦で使う兵器として研究を始めたんだからな。それに、小さくても国は国だ。城に侵入した間者を拷問するための部屋……、あってもおかしくない」
久々知の言葉を肯定するように彦兵衛は深く頷いた。
拷問部屋―――研究室で見た光景は、とても直視出来ないものだった。躯になって朽ちていたそれは、指が全部無くなっているものだったり、鼻や耳が削げていたり……。四肢をもぎ取るかのように鎖で磔にされているものもあった。今は物言わぬ屍だが、拷問されていた当時はどんな断末魔の声を上げていたのだろうか。まさに正気とは思えない地獄絵図だ。
特に暴力を嫌っているは、この事実を受け止めきれず肩が震えてしまう。
(ダメ、しっかり話を最後まで聞かないと……)
「それで、あの城はなぜ廃城になったんですか?」
「!」
雷蔵がの肩をぎゅっと抱き、彦兵衛に問いかけた。雷蔵の体温と彼の気遣いにの心は落ち着きを取り戻していった。そして、改めて彦兵衛の声に耳を傾けた。
「2つの国に分かれてしまう原因になった事件―――【鬼姫の祟り】が起きたためだと聞いておる」
「お、鬼姫……」
全員の心臓が大きく脈打った。ここまで何度も達が聞いてきた呼び名だ。他国からも恐れられている、赤い眼をした異形の姿の姫。ぽつりと思わず声を漏らしたに震えが走る。
「初代の鬼姫と呼ばれた、赤眼病患者の姫様―――朔姫様が起こした祟りです。朔姫様は、拷問にも等しい実験により鬼化してしまった」
「拷問……。何て酷い事を……」
人間兵器になるための実験で自由を奪われ、身体を傷つけられた。さぞや強い怨嗟の念を抱いていただろう。
は放置された屍の、惨たらしい姿を思い出して青くなる。
「朔姫様は、これまで鬼化した赤眼病患者の誰よりも驚異的な身体能力を持っていたそうです。そして、目に入る城の者達を次々に引き千切り、嬲り殺しにしたと……」
「なっ、何だよそれ……!?人間を引き千切る!?じゃあ、オレ達がいたあの城は……!?」
「惨劇の舞台になったようだな」
「鬼化した人の強力な能力は、僕らも知っているからね。だけど、城の人達を皆、って……」
「そういえば、城に入ったとき、腕や足、頭だけの骨が落ちていたからな……」
「ええ?!マジかよ?!」
「そんな……!?三郎くん、それ本当なの……?」
「姫サンを怖がらせたらいけないと思って黙っていたが、城にはいくつも不自然な骨が転がっていた」
「もしかして、私に急に近づいてきたとき……?」
「ああ。結局姫サンが怖がる事になってしまったけれどな」
「ううん、そんな事無いよ。ありがとう、三郎くん」
廃城の中へ入った直後、三郎の様子はどこかおかしく感じていた。今その意味を理解して、は三郎の不器用な気遣いが有難く思えた。もし、あのときが人間のバラバラに散らばった骨を見ていたら、廃城の中で留まるなど出来なかっただろう。
鬼化すれば鬼神のごとし力を手に入れるという赤眼病。例え朔が子供だったとしても、熊のように鋭利な爪を使い、素手で人間を殺すことも簡単だっただろう。
「記録では、城の者達は半数以上、暴走した朔姫様に殺されてしまったそうです。床には惨殺された者達の血が溢れ、足首まで浸かったと記されておりまする」
「ははは……。確か、床が妙に黒かったよな……」
「…………」
床が朽ちていたり薄暗い城内だったので気づかなかったが、恐らくあの黒ずみは血が海となって床を濡らした跡だ。
竹谷が乾いた笑い声を零し、その床に触れてしまった久々知は、自分の両手を見て複雑そうな表情を浮かべている。
は気を引き締めるために一度深呼吸をする。落ち着こうと自分に言い聞かせながら、は彦兵衛を見据えた。
「彦兵衛さん、バラバラになった遺体を考えれば、人間の力とは思えないほどの力を朔姫は持っていたと思います。鬼化した朔姫と城はどうなってしまったんですか?」
「朔姫様の従兄弟君―――有明様が、朔姫様をたったお1人で討ったと伝えられています」
「鬼姫を討った?!1人で?!」
「それ本当ですか?!信じられない……!」
「本当に?!」
驚きのあまり、竹谷も雷蔵も信じられない様子で彦兵衛の話に食いついた。も驚きのあまり目を丸くしてしまう。
「鬼化したヤツって言うなら、あの新月丸だろう?結果的にオレ達は新月丸とは直接戦わなかったが……」
久々知は怪我で本調子ではない左腕を擦る。強力な暗示をかけられていた食満に腕を折られたのだが、もしあれが新月丸本人だったとしたら、擦る腕は失っていただろう。
「もし戦っていたら、間違いなく全員殺されていたじゃろうな」
「新月丸のあの姿を見れば、戦わなくても勝てないって感じだったよな。でもまぁ姫サンをあのまま傷つけるつもりなら、それでも私達全員で戦う覚悟は出来ていたがな」
「だよな!……その後で1年坊主みたいにちびってたかもしれねぇけど」
「ハチ、せっかく私が格好良く決めたのに、情けない事を言うなよな〜」
「八左ヱ門なら間違いなくちびっていただろう」
「それに加えて、生まれたての小鹿みたいにブルブル震えちゃっただろうね〜」
「おっ、お前らだって絶対にちびるだろ?!小鹿になるだろ!?バンビ!!」
「お主達、話が脱線しておらぬか?」
「……多分、私を少しでも怖がらせないようにしているんだと思います」
こそっと彦兵衛にが告げると、『やれやれ』と呟きながらも皺だらけのその目元が柔らかくなる。それからわざとらしい咳払いをした後、話を続けるため口を開いた。
「わしも詳しい事は存ぜぬが、有明様は朔姫様を討ち取った後、赤眼病の研究推進派に反発をして袂を分かったのじゃ。そして、この光陽国を有明様が建国されたと記録には残されておる。鬼となった朔姫様が討伐されてもなお、朔姫様の祟りを恐れた城の者達は、凄惨な現場となった城を捨てた。その後、月陰国という新たな国と城を造った……と」
「それが、光陽国と月陰国が出来た経緯なんですね……」
「はい、様のおっしゃるとおりです。その後は小競り合いが起きる度、光陽国と月影の国の当主の子を人質を交換し、国を治めてきました。十六夜姫様のように……」
新しく知る過去の出来事はあまりにも衝撃的なもので、も5年生達も沈黙してしまう。あのおぞましい研究室の扉を開かなければ、恐らくの耳にも届かなかったことだろう。
しかし、の頭に【後悔】の2文字は浮かばなかった。
「彦兵衛さん」
「はい」
「この国の、誰にも知られたくないような黒く淀んだ部分……。それを話してくださって、ありがとうございました」
淀みのない透き通った瞳が、彦兵衛の目に眩しく焼き付いた。
がしっかりと前を見据えた後に深くお辞儀をすると、それに5年生も倣う。
彦兵衛は、の今の表情を見てこう思う。
(良い眼をする御方じゃ。この御方が、十六夜姫様の遺した希望なのですな……)
「さん、まだ起きていたんですね」
「兵助くん……」
夜中、が井戸の水を飲むために廊下を歩いていると、夜着姿の久々知に出会った。井戸は深く危険だからと、久々知も一緒について来てくれた。さわさわと夜風が2人の髪を撫でた。
「さっきの彦兵衛さんの話を聞いて、何となく目が冴えてしまったみたい」
「実はオレもです。少し話でもしましょうか」
「うん、そうだね」
久々知が井戸の水を汲んでくれる。柄杓で飲む水は心地良い冷たさだ。喉がうるおい、は一息ついて夜空を見上げる久々知を見た。夕方の雨雲は消え失せ、美しい満月が顔を出している。今夜の月は美しいだけではなく、寂しさと悲しみを感じた。
「彦兵衛さんの話、どう思った?」
「非常に恐ろしい話でしたね。あの廃城は、ようするに鬼姫に殺された人達の墓場という事です。この乱世では、あのような惨劇は五万とある話ではありますけれど。人を鬼に変える赤眼病も、鬼になった朔姫も、拷問まがいの研究を続けてきた関係者達も、恐ろしくおぞましいです」
「私は……朔姫が可哀想だと思ったよ。赤眼病の実験の被害者なのに、【鬼姫】って呼ばれて、従兄弟に討たれて、亡くなった後もずっと恐ろしい存在だって伝えられて……。朔姫が鬼になりたくてなったわけじゃないのにね」
は鬼化したときの自分自身の変化を思い出し、身体が震えてしまう。徐々に恐ろしい化け物へ変化していく身体。自分が自分ではなくなってしまう未知の恐怖は、今でもの脳裏に鮮明に焼き付いている。そして、城の者達から恐れの視線を向けられ、息苦しくなった事も。もし、拷問という衝撃的なストレスから鬼化したのだとすれば、は朔に心から同情する。
「【鬼姫の祟り】は、無慈悲な研究や実験を繰り返した者達への警告だったのかもしれませんね。これ以上、非道な事を続けてはいけないと。でも、人は愚かだから、例え城の人間が半分以上犠牲になってしまっても、強力な人間兵器という魅力に取りつかれてしまった……」
「負の連鎖を止めるために、十六夜姫と新月丸さんは遺伝する赤眼病の血を絶つための決断したんだね。赤眼病の遺伝子を持つ人物は、もうこの世には存在しない」
「結局、赤眼病を完治させる前に患者が全員亡くなったわけですからね。これまでの実験も研究も無意味だったという事でしょうか……」
「ううん、そんな事ない。元々は病気を治すための研究じゃなくて、人間兵器を作るためのものだったんだから、終わっただけでも意味がある事だよ。人間兵器は作られなくなるし、どうしようもない負の連鎖を断ち切れたんだから、後はきっと良い方向へ進むだけだと思う。過去は変えられないけれど、未来はこれから変えていけるんだもの!……あ、でも……」
「どうしたんですか?」
意気込んでいたが急に小さくなった。久々知がその様子に首を傾げていると、は頬を指で掻いて俯いてしまう。その表情は美しい夜空とは対照的に曇っていた。
「私、もう十六夜姫じゃないし、光陽国でお世話になっている立場のくせに何も出来ていないよね。いつか元の世界に帰るとしても、少しは役に立てたら良いな……って」
「彦兵衛殿は、さんを役に立つとか立たないとか、そんな事を思っていないですよ。今は光陽国も月陰国も大変な時ですし、人手が少しでも多い方が良いはずです。さんは光陽国と月陰国の戦を未然に防いだ立役者ですから、いてくれるだけでも城内の士気が高くなりますよ」
「そ、そうかな……。そうだったら良いな。私、もっと頑張るね!」
月に煌々と照らされるの照れる顔は、見ている久々知にも笑顔をもたらす。
久々知はに自分の羽織っていた上着を着せる。急にぬくもりが肩に降りてきて、はぽかんとしてしまった。年齢よりも幼い表情を見せたに、久々知はくっと笑い声を零す。
「そろそろ寝ましょう。部屋まで送ります」
「うん、ありがとう」
「さんを見ていて、少しオレの同室のヤツを思い出しました」
「同室の子?それって、兵助くん達と同じ5年生?」
「はい。落ち込んだと思ったら直ぐに元気になって、菓子が大好きなヤツです。きっとさんの作った菓子を食べたら、沢山おかわりを要求してくると思いますね」
「へ〜。賑やかな子なんだね。それに食いしん坊」
「忍術学園へ来る機会があれば、そいつの事も紹介しますよ。きっとさんの事を歓迎してくれると思います」
「それは楽しみ。兵助くんの同室の子か、会ってみたいな」
はまだ見ぬ久々知の同室の少年を思い、目を細めた。
静かに夜は更けていく。
そして、
今日を境にの穏やかな日々は、
再び不穏な騒がしさに包まれるのだった。