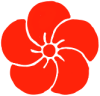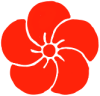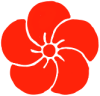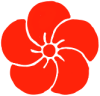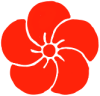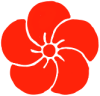第一夜 森の影になった廃城
「様!?」
朝の光陽国の城内。台所で彦兵衛の困惑する声が響いた。名前を呼ばれた少女は『あ』と気まずそうに振り返った。
臙脂色の小袖を纏い、襷掛けに白い前掛けを着けたその姿は、まるで城内をせこせこ動く侍女のようだ。ただ1つ違うのは、長い黒髪ではなく、短い癖のある薄茶色の髪だという事くらいである。
「あー……、あの、彦兵衛さんも食べますか?カステラですけれど……」
の持つ皿の上に鎮座しているのは、南蛮から伝わった菓子―――カステラだ。
黄金色に艶々と輝き、出来たてなのか湯気がほこほこと湧き上がっている。甘じょっぱい日本人好みの香ばしい匂いがして、思わず齧り付きたくなる。の腕前を知るだけに、彦兵衛はゴクリと唾を飲まずにはいられない。
だが、しかし、例え極楽を味わえようとも、彦兵衛はコレを拒絶しなければならなかった。
「様っ!あれほど侍女のような姿や振る舞いをお止めくだされと、あれほど申し上げたはず……!台所はここにいる侍女等に任せて―――」
「私の作った物を食べたいと頼まれたので……」
見れば台所にいる侍女たちは各自の手にカステラを持ち、はしたなさも気にせず頬張っている。そのうっとりとした様子に自分も食べたくなるが、彦兵衛はこの城の重鎮としてぐっと我慢しなければならない。悔しさも込めて侍女たちを叱り付けた。
「お主たち、様に何をさせておるのじゃ!!」
「様の作られるお菓子がどれも絶品なのです。それがいけないのです!」
「様のせいにするでない!」
「本当に美味しくて、私たちも参考にしたかったんです!研究のためです!」
「それはお主等がただ食べたいだけであろう?!」
「そうとも言います」
「そうとしか言わぬわっ!!」
「あ、勿論お菓子だけでなく、他のお料理も美味でしたわ」
「この前作ってくださった『はんばぁぐ』なるもの、今度ぜひ教えてくださいませね」
「はい、私の作り方で良ければ」
「様っ!」
「……はぁい」
は困ったように小さく笑い、彦兵衛と台所を後にした。
のためにと用意された部屋―――十六夜の私室へ連れて行かれる。が上座だというのに、彦兵衛の方が威圧感をビシビシ飛ばしていて、思わず視線を泳がせてしまう。
「様、先ほども申し上げましたが、侍女のように給仕をするのはお止めください。様に侍女のような事をさせるなど、国の恥にございます!」
「く、国の恥?!そんな……、私はここでお世話になっている身分ですから、何もしないわけにはいきませんよ。国の恥だなんて、大げさです」
「そんなわけありますまい!様は光陽国と月陰国の戦を止めた救世主様です。大恩ある御方に給仕をさせるなど、とんでもない!」
「は、はぁ……」
他の侍女たちと混じって台所に立っていたこのごく普通の少女―――は、彦兵衛の言葉にピンときていない様子だ。
【光陽国】と【月陰国】は、何か諍いがある度に人質を交換して戦を避けてきた。
月陰国から養女に出された一の姫である十六夜は、通称【鬼姫】と呼ばれ、恐ろしい噂が付き纏っていた。
近年月陰国が光陽国との戦を仕掛ける大義名分として、十六夜の暗殺を企てているという情報が入った。そこで、忍術学園の5年生を十六夜の護衛に付け、戦を避ける事にしたのである。
だが、ここには大きな誤算があった。それは、十六夜が十六夜ではなく、という全くの別人だったのだ。
そして、なんやかんやで戦をが止めた。
「なやかんやって……」
「様?」
「あ?!ごめんなさい、何でもないです」
思わずモノローグにツッコミを入れてしまうところだった。
「……彦兵衛さん、私は自分からこの国を救おうとか考えたわけじゃありません。ただ、5年生の皆に護られるだけじゃ嫌で、私も護りたくて……。ようは成り行きです。だから、救世主とか、そんなすごい人じゃないですよ」
そう、の言うように、完全な成り行きだった。誰かに頼まれたわけでもなく、使命感に燃えたわけでもない。ただ、の大切な人たちを護りたい、護られるだけの存在になりたくなくて行動したのだ。本人は、自分を彦兵衛の言うような特別な存在だとは考えていない。それが返って彦兵衛に感動と感激の渦に引き込んでしまうとも知らずに。
「様ー!!」
「は、はいっ?!」
「この彦兵衛、大変感激致しましたぞ!国をお救いになったというのに、なんと謙虚な……!」
「失礼致します」
襖の向こうから侍女が声を掛けてきた。この部屋に来たという事は、に用事なのだろう。彦兵衛はが最優先だ。『入れ』と短く答えれば、恭しく頭を下げて侍女が姿を見せる。この侍女は十六夜姫付きの侍女で長年仕えており、彦兵衛にとっても信頼に値する侍女だった。
「様、お帰りになられましたよ」
「!」
は返ってきた人物が誰なのか直ぐに理解し、顔をパッと明るくする。それから訴えるようなの視線に、敵わないと彦兵衛は目尻に笑い皺を作った。
「忍の者たちでしょう?わしに構わず、会いに行ってくだされ。わしとはいつでも話が出来ます故」
「ありがとう、彦兵衛さん!」
は立ち上がって客間へ向かおうとする。私室の襖に手を掛けたところで、『あっ』と何かを思い出したように振り返った。
「彦兵衛さんの分のカステラも作ったんですよ。後で食べてくださいね」
にこっと微笑み、は今度こそ私室を出て行った。カステラの甘い香りを残して。
侍女はくすくすと笑いだす。
「様、すっかり彦兵衛殿のお孫様のようですね」
「何を申すか。様はこの国の大恩人であり、わしのような者の孫になろうはずがない」
「あら?その割にはお顔が緩んでいらっしゃいますよ?」
「そこは流せ」
「ふふっ」
穏やかな空気に包まれる。ここ何年か光陽国では感じられなかったものだ。
十六夜の入城、城主の暗殺、十六夜が病に伏せ、そしてつい最近は十六夜の暗殺計画と月陰国への誘拐……。光陽国の民全てが不安の渦中に引きずり込まれた。
月陰国との和平を共存を決めた今、前へ進むためにもやるべき事が山積みである。
彦兵衛は侍女と親しげにするの姿を思い浮かべる。そして、重なる今は亡き主君だった少女。
(これから先、あなた様以外にお仕えする事をお許しいただけるのだろうか……)
この場にもし十六夜がいたら。
返ってくる言葉など、とうにわかっていた。
が客間に到着すると、5年生の4人が待ち侘びたように顔を綻ばせて駆け寄ってきた。普通なら忍者である彼らにそのような振る舞いを許さないのだが、家臣や侍女たちは気を利かせて出て行く。
本来彼らは十六夜の護衛が終われば直ぐに忍術学園へ戻るはずだった。しかし、十六夜の護衛後も2つの国の内政は混乱が続くことは目に見えていた。だから光陽国と月陰国の架け橋となる手伝いをするため、そのまま光陽国に残ることにした。忍術学園も今回の事件で被害が出ているので一度帰るべきなのだろうけれど、学園長からも無事に光陽国へ居残る了承を得られた。
彼らは光陽国の書状を持った使者の護衛のため、少しの間月陰国へ出かけていた。これからの光陽国と月陰国の内政に関わる重要な書状だったこともあり、彦兵衛の信頼を得ている彼らが適任だと判断されたのである。
ちなみに今回の事件で怪我をした雷蔵と久々知は城での休養を勧められた。しかし、殆ど治っていたこともあり、『忙しく働いている臣下ばかりの城内では、休養なんて出来ない』と護衛の忍務に参加した。
竹谷はの手をぎゅっと握った。の温もりが伝わってきて、竹谷の顔が嬉しさに綻ぶ。
「!5日振りだな!元気にしてたか?」
「うん、勿論元気だったよ!八左ヱ門くん、皆もお疲れ様!」
「その恰好ではな。よほど元気に動き回っていたんだろう」
おかしそうに笑って、三郎はの前掛けを摘まむ。は自分が侍女姿だった事に気づき、恥ずかしそうに言った。
「あはは……。早く皆に会いたくて、この恰好のまま来ちゃったよ」
「客人という立場なのに、姫サンは侍女の真似事をして忙しいな」
「これまでが大変だったのだから、もっとゆっくり過ごしても良いのでは?城内が混乱していたとはいえ、事情はもう説明してあるんですよね?」
「うん、一応はね」
久々知の問いかけに、はこくりと頷いた。
十六夜から元の姿に戻ったは、光陽国の城で目を覚ました。成り行きとはいえ、これまでの十六夜はが演じ、不本意だったが周囲を騙してきた。その事実を明かし、彦兵衛に精一杯の謝罪をした。
今まで仕えていた主人が実は別人だったなんて、とても信じてもらえないとは思った。しかし、赤眼病や十六夜姫の予知能力など、通常では考えられない出来事は以前から体験済みの彦兵衛は、を受け入れた。のことを、生前の十六夜が予知夢で見ていた救世主であると確信した。何より、のこれまでの清廉な振る舞いは、信じるに値するものだった。
家臣たちに正式に紹介されたは、戸惑いを与えたものの、彦兵衛の働きかけによってどうにか受け入れられた。
「私の事は、『十六夜姫が大変お世話になっていた知人で、今回の月陰国との混乱を治めた人物』という事になっているよ」
「確かに、さんの本当の事情を説明するのは難しいですよね。僕たちも最初は理解するのが難しかったですし……」
「というか、正直オレは今も良く理解していないけれどな!」
「八左ヱ門、それは明るく言う事じゃないぞ……」
「それを言っちゃうと、私自身あまり理解していないんだけれどね〜……」
は困ったように笑うしかない。
不思議なことに、この世界へ来る直前の記憶が抜け落ちている。何度もは思い出そうとしたが、その度に頭の中に靄が現れ、上手く思い出す事が出来ないでいる。がいた世界からこの世界へ飛ばされた切っ掛けが、その直前の記憶に含まれているはずだというのに。
(私がこことは違う世界から来たっていう話は、結局忙しくて皆にもしていないんだよね)
がこれまで十六夜の姿をして本人のように振る舞っていたことについては説明してある。だが、光陽国と月陰国の混乱や復興で忙しく、彼らに話す機会がこれまで無かったのだ。それに、この城内でこの話題を打ち明ける事は出来ない。はこの城の客人として滞在しているが、もし異世界から来た者と知られれば、信じる信じないを別としても怪しむ者が出てくるだろう。これ以上の混乱は避けたい。
(皆も、何となく私がこの世界の人間じゃないことは薄々気づいていると思う。でも、いつ話したら良いのか……)
言い出す機会が無かった事は本当だ。しかし、が無意識に避けていたのもある。
が異世界の人間である事を話す。
それは、つまり―――
(いつか、皆とお別れしないといけないかもしれないって事なんだ)
それがどんな形になるのかはわからない。それに必ず帰れる保証も無い。
だが、少なくともは自分の世界へ戻らなければならないと思っている。
「今夜は確か宴を開いてくれるって聞いたな」
三郎の言葉での心は現実に戻ってくる。
「う、うん、そうだよ。使者護衛の忍務が終わって帰ってきたら宴にしよう、って」
「うおー!それは楽しみだな!」
「宴って言っても、私たちと彦兵衛さんだけの小さな宴なんだけれどね」
「僕たちが姫様の護衛忍務をしていたことは、一部の人しか知りませんからね」
「大々的にやるより、オレたちだけでやる方が思いっきり楽しめるだろ!おーっし、食べるぞ〜!」
「光陽国のご飯は食堂のおばちゃんに負けないくらい美味しいからな。私の好物も出して欲しいところだ」
「豆腐はありますか?」
「あはは、兵助は本当にそればっかりだよね……」
「どれも沢山美味しいものを用意くれるらしいから、楽しみにしてて!」
が満面の笑顔を見せると、彼ら4人も同じ笑顔で返事をした。
こんな風に彼らと笑い合えるようになろうとは、が十六夜姿だったときからは想像も出来ない。しかし、これが今現実になったのだと思うと、は嬉しくてたまらなかった。
三郎がふと空を見上げた。抜けるような青空が見下ろしている。まだ太陽は登り切っていない。
「宴までにはまだ時間があるよな」
「まぁ、宴は夜だからね」
「姫サン、だったら夜まで少し出かけないか?」
三郎はニッと歯を見せて笑う。好奇心に溢れた目は、14歳そのものだ。
は三郎の申し出に少し戸惑った。
「え?だけど、皆ついさっき帰ってきたばかりで疲れてない?」
「ああ、それでしたら大丈夫ですよ。実は城下近くの宿で休んでから来たので、全然疲れていないんです」
言われてみれば、兵助の恰好は薄汚れてはいるものの、疲れの色は伺えない。
「姫サンは、姫サンだったときも城の客人になった今も、外へ出ていないだろう?だから少しは息抜きも必要だ」
「光陽国の城下町は今回の事件で少し騒ぎもありましたが、活気があって良いところでしたよ。何より豆腐が美味しいです」
「全然ブレないよね、兵助は」
キラキラと目を輝かせている久々知に、もはや雷蔵は笑うしかない。
「うん、知ってる。少ししか城下は歩いていないけれど、私も賑やかで素敵なところだなって思ったよ」
「ああ?!そういえば、は一度城下にこっそり抜け出したんだったな」
「そういえばそうだったな。私たちのために団子を買ってくれたんだった」
「だったら、そのお団子屋さんに行かない?結局あのときは持ち帰れなかったから……。皆と一緒に食べたいなって思ってたの!」
「「「賛成!」」」
こうしてたちは宴の時間まで城下町へ出かけることにした。
もちろん彦兵衛からの外出許可を取った。彦兵衛もを外出させてやりたいと思っていたのだが、の護衛につけられるような人員を割くことが出来ずにいた。だから、5年生たちが城へ戻ってきてくれて大いに助かっている。
城下町へ足を運んだたちは、思い切り城下町の活気ある雰囲気を楽しんだ。
大人気の団子屋で食べた団子は、の世界でも食べた事のないような絶品だった。香ばしく甘じょっぱい醤油味と、きなこの優しい甘さの団子のもちもち感を舌の上で楽しんだ。気付くとたちの周りには団子を食べた皿の山が出来てしまっていた。『宴の分までお腹いっぱいになっちゃいそうだね』と皆で笑い合った。
その後城下町を色々見て回った後、近くにある森へ遊びに出かける事にした。
都会育ちのにとって、森で遊ぶ事はとても新鮮に感じた。緑深い森の空気はすっと肺に入ると心地良く思えた。竹谷と一緒に綺麗な色の鳥を探したり、雷蔵に見た事のない植物の名前を教えて貰ったり、三郎と兵助は川で魚の捕まえるところを見せてくれた。
どれもこれも現代や城では体験出来ない事だったので、は目を幼子のように終始輝かせていた。それを見て、彼らも嬉しくなる。は、十六夜のときはずっと険しい顔をして過ごしていた。のこれまでを想うと、彼女を楽しませる事が出来て心から嬉しいと思った。
清流の近くで火を起こすと、三郎と兵助が採ってきた魚を焼いた。香ばしい匂いが鼻を通して空の胃袋にまで入り込むようだった。
「、焼けたぞ。ほらっ!」
「熱いから気を付けてくださいね」
「わ〜〜、ありがとう!いただきますっ!」
雷蔵から手渡され、は枝の串に刺さった焼き立ての魚に齧り付いた。じゅわっと舌に広がる脂身と、柔らかい身が口いっぱいに広がる。
都会育ちのにとって、このように串の魚を食べる事は初めてだ。思わず頬が緩んでしまう。の口に合うかどうか気になっていた彼らも、の幸せそうに頬張る姿を見て安心し、自分たちも魚を食べ始めた。
「ハチ!お前、自分だけ1番大きいものを食べていないか?!」
「オレが釣ったんだから当然の権利だろー!」
「お前は普段から良く食べているだろう」
「生物委員会は常に脱走した動物や毒虫を探し回ってるんだから、腹が減るのは当然なんだよっ!」
「せっかくなんだから、さんに大きい魚を食べさせてあげたら良かったのに……」
「そんな、気にしないで雷蔵くん。この魚だってすごく美味しいよ」
確かにの魚は竹谷のよりも少し小さい。しかし、それでも十分腹を満たしてくれる大きさだ。
ふと、は昔聞いたある話を思い出した。
「皆は、魚をこうして外で食べる事は多いの?」
「ん?ああ、そうだな。実習で魚を獲る方法も教わるから、そのときに食べる事もある」
「そっか。じゃあ、お餅は外で食べたりしない?」
「餅?」
三郎がきょとんとした顔で聞き返すと、は懐かしむような顔で言った。
「うん、お餅。昔ね、すごく仲の良い友達が言ってたんだ。『川で釣った魚を焼いて食べるのも好きだけれど、お餅をこっそり持ち出して、河原で焼いて皆と食べるのが好きだった』って……」
「へぇ、お餅ですか。僕たち、お餅は特別な祝い事やお正月にしか食べませんよ」
「そうなんだ」
久々知は食べ終わった魚の骨を火の中に投げ入れながら言った。
「こっそり持ち出して食べるなんて、村なら大変な事ですよ。村の決まりを破る事になるでしょうし」
「えっ?!そんなに大変な事なの!?」
「年貢米を治める都合もあって、許可も取らずに餅を持ち出して食べるのはなぁ……。あ、でも、私も1人知っているぞ。餅を勝手に食べそうなヤツ」
「……あ〜、いたなぁ」
「確かにやりそうだよね〜」
「ああ、そうだな」
「?」
三郎、竹谷、雷蔵、久々知は、お菓子が大好きでうどんのような髪をした級友の姿を思い浮かべた。ヤツならばやりかねない、と。
「いや、オレたちと同じ5年生で、の言う友達のようなことをしそうなヤツがいるんだ」
「お菓子が好きで、食事当番のときなんかはつまみ食いをすることもあるんですよ。オレの豆腐料理は一切食べませんけれどね」
「この前だってアイツはおばちゃんに怒られていたな〜」
「姫サンの護衛に来ていたら、城の台所は面倒な事になってたかもな」
「あはは、そうだね〜」
悪口とも捉えかねない内容なのだが、彼らがその級友を好ましく思っている事は、その表情から伝わってくる。とても仲が良いのだろう。ワイワイとこの場にいない級友について盛り上がり始めた。
「へぇ、何だか私の友達に似ているかも。皆の言うその子は何ていう名前なの?」
「ああ、そういえば話していなかったな!」
「私たちと同じ5年生で、名前は―――」
そのときだ。の鼻の頭に、ぽつんと雫が降ってきた。空を見上げると、いつの間にか厚い雲が太陽を覆い隠している。川の近くにいたせいで気づかなかったが、雨の湿った匂いが混じっている。やがてぽつぽつと雨がたちの頭上へ本格的に降り始めた。
「やばっ!雨が降ってきた!」
「うわっ?!冷たいっ!」
竹谷と三郎は食べかけの魚を一気に食べてしまう。
「これは結構本格的に降ってくるな」
久々知は鬱陶しそうに手を翳しながら空の様子を見る。冷たい雨が頬に打ち付け、視界が悪くなっていく。
「水嵩が増えると危険だ。皆ここれから離れるよ!」
雷蔵はそう言って、持って来ていた手拭いをの頭に被せた。
「雷蔵くん、私は大丈夫だから雷蔵くんが使って!」
「僕、湿気で髪が爆発するから手拭いは被れないんです」
「え?それってどういう―――わっ?!雷蔵くん、その頭どうしたの?!」
「相変わらずすごいな〜雷蔵の髪!」
雷蔵の髪は気付けば倍に増えていて、竹谷がゲラゲラと笑い出してしまった。初めて雷蔵の爆発ヘアを見たは、思わず凝視してしまう。
「私今爆発した雷蔵のヘアピース持ってきてないのにっ!」
「それより早く雨宿り出来そうな場所を探すぞ。本格的に降ってきたからな」
久々知はの手を取って小走りに森を走り出した。慌てて他の3人も後に続く。
雨雲のせいでまだ夕方前だというのに森が暗く感じた。雨音が一層激しくなって、たちの肌にじめっとした嫌な感触が伝わってくる。足元が悪くなってきて、何度も転びそうになったが、どうにかは踏ん張った。
薄暗くなった森の中、正面にチラッと影の濃いものが見えた。一瞬それは崖にも似た崖のように見えたのだが、良く見ればそれは朽ちた石垣だった。
「石垣?こんなところにどうして……?」
「姫サン、見上げてみろよ」
「えっ?もしかして、これはお城……?」
雨のせいで視界が悪いが、石垣の積まれた上には薄汚れて蔦や苔生した壁が見える。ところどころ崩れており、簡単に敷地内へ入れるだろう。その先に聳えているのは、雨風を長年受けてきた廃城だった。それは光陽国の城にも似ているけれど、この城の方がずっと大きく感じられる。何より、底知れない薄気味悪さを感じた。体が冷たくなっていくのは、雨のせいだけなのだろうか。
(森の中にこんなに大きな建物があったら、普通気づくはずなのに……)
まるで森の影になってしまっているような廃城だ。
不気味な廃城で気は進まないものの、雨に濡れた今、ここで雨宿りをする選択も出来る。
「ねぇ、この中で雨宿りしない?ここなら何とか雨は凌げるだろうし……」
「いや、ここは危険です。廃寺やこういう廃城は、山賊が住処にしていることが多いんです」
「兵助、それはそうだが、このまま雨に濡れてたら風邪を引いちまう。何かあっても、の事はオレたちで護れば良いだろ」
「確かに、ここで出来る選択は1つだけみたいだな」
三郎は懐に忍ばせている武器を確認する。既にこの付近にも山賊が隠れているかもしれないのだから。
「さん、万が一という事もあるので、僕たちから離れないでくださいね」
「うん、わかった……」
もしも山賊が潜んでいれば、戦いは避けられない。そうなったときに、は足を引っ張らないように気を付ける必要がある。
は少し緊張した面持ちで、こくんと頷いた。
雨の音が支配する中、彼らは廃城の敷地へと足を運んだのである。